退職の手続きが終了し肩の荷が下りたかと思ったら、急に業務連絡が来たという話を耳にします。
退職したにも関わらずなぜ業務連絡が来るのだろう、と疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
転職準備も忙しいのに、前職からの業務連絡には応じなくてはいけないものなのでしょうか。
退職後の業務連絡に応じることは義務なのか、また退職に関してのトラブルやその回避方法も併せて確認しておきましょう。
次の仕事を気持ちよく始める為にも、気持ちのいい退職をしたいものです。
Contents
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
退職後の業務連絡には応じるべき?
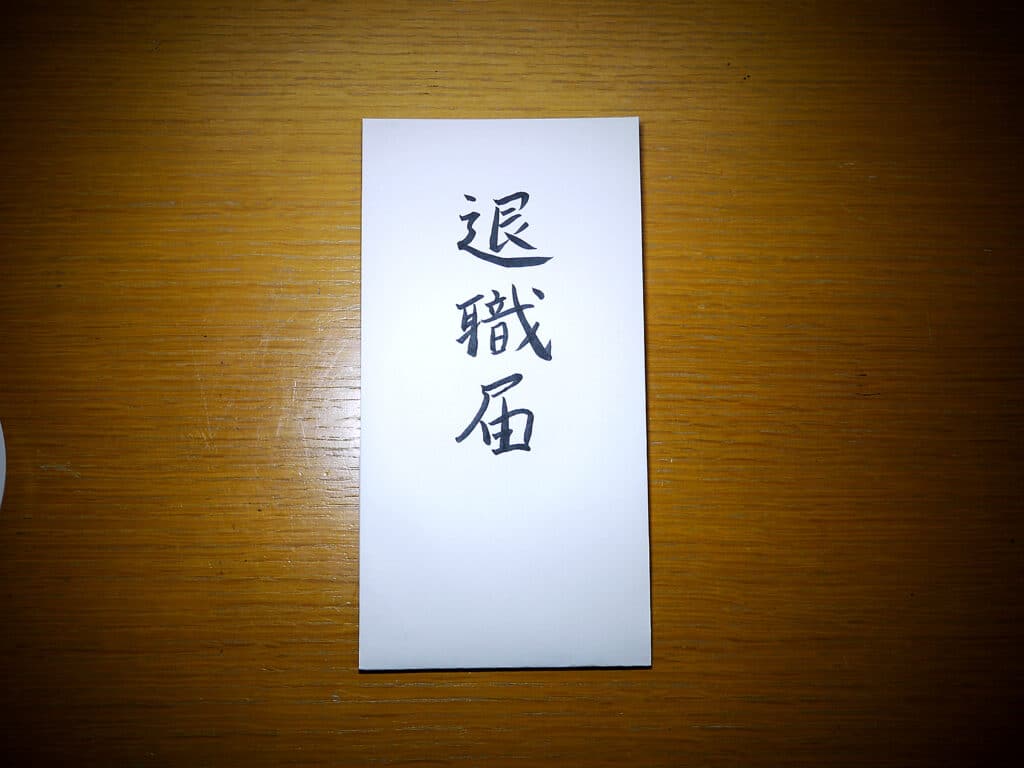
退職は契約上、会社と無関係になることを意味しています。
退職した人の気持ちも、既に次の人生へと向いているのではないでしょうか。
そこへ前職からの業務連絡が来るのは、対応すべきか頭を悩ませるところです。
実際「退職後に仕事関係の連絡がきて困っている」という声がよく聞かれます。
しかし退職後の業務連絡について、対応の仕方は内容次第といえます。
自分の在職中のミスで業務に支障が出ている場合や、企業から借りていたものを返却していなかった場合などは、しっかり対応しておきましょう。
一方、退職しても仕事関係の連絡が来るのは対応をしなくてもいい、というのが結論です。
退職してからの業務連絡について、更に詳しく見ていきましょう。
退職後の業務連絡で多い内容は

退職後の業務連絡に悩んでいる人は少なくありません。
具体的にどのような内容の業務連絡が来るのか、代表的なものを見ていきましょう。
退職手続きが完了していない
退職手続きの中では、離職票がなかなか届かないという場合が多いようです。
離職票や退職証明書は、転職先で必要となるケースもあるので出来るだけ早く手元に用意しておきたいものです。
その他、源泉徴収票(退職後の1ヶ月以内)や雇用保険被保険者証、年金手帳などの受け取りを忘れていると連絡が入ります。
また、離職票などがなかなか届かない場合は、催促の連絡を自ら入れることになります。
業務の引き継ぎに関して
退職後の業務連絡で最も多いのが、業務の引き継ぎ関係です。
企業を既に辞めているのに、仕事に関する様々な質問をされたり中にはパスワードなどを聞かれたりするケースもあります。
引き継ぎをきちんと出来ないまま退職してしまうと、これらの連絡が頻繁に来てしまうこともあるようです。
初めは仕方がなく対応する人も多いようですが、あまりにも頻繁に連絡が来ると少々うんざりしてしまう、という声を耳にします。
前職での仕事の内容にもよりますが、100パーセント完璧な引き継ぎを行うことは至難の業です。
しかし、退職後に自分への質問が来ないような引き継ぎをしておきたいものです。
貸与備品などの返却忘れに関して
意外に多いのが、企業から借りていた物の返却ミスです。
こちらは自己責任になるので、連絡が来た際には速やかに対応しましょう。
企業によっては持参する事を求めらることもありますが、事前に郵送する旨を伝え郵送すれば問題ありません。
企業や個人の情報に関するものは書留などを利用するなど、郵送のマナーを守りましょう。
健康保険被保険者証やIDカードなどが返却の対象になりますが、忘れがちなのが名刺です。
取引先などと取り交わした名刺なども返却の対象となるのでお忘れなく。

退職後に業務連絡に対応する義務はありません。
あまりにも頻繁に連絡が来たり、仕事の内容を細かく聞いて来たりする場合は、対応出来ない旨をしっかり伝えてもいいのではないでしょうか。
しかし引き継ぎ対応を拒否して全く引き継ぎを行わず退職した場合、企業が損害を受けたとして損害賠償請求をされることもあります。
仕事の引き継ぎは社会的な常識なので、しっかりと引き継ぎをしてから退社するようにしましょう。
どうしても引き継ぎが不十分のまま退社してしまった場合は、対応に関しては常識の範囲内での自己判断ということになります。
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
退職時に注意すべき点
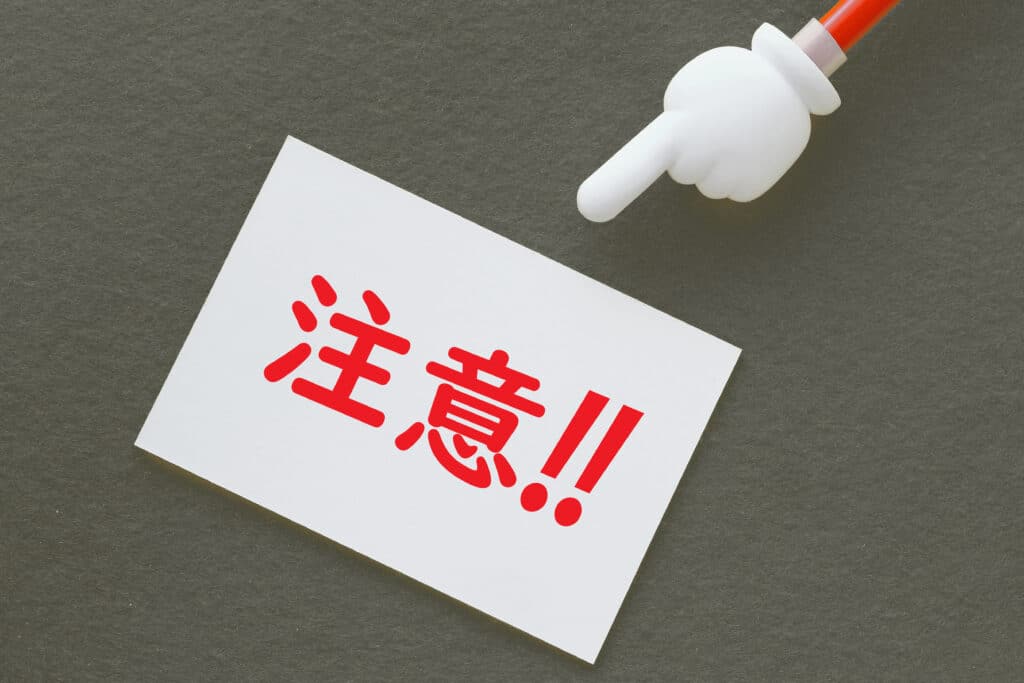
退職はそうそう経験するものではなく、大半の人は手続きや引き継ぎに追われてしまいます。
退職を決意したら、まずは冷静に下記の注意点を念頭に入れておきましょう。
引き継ぎのことも考え繁忙期に退職は避けよう
引き継ぎは実際に行ってみると、自分が想像をしていたよりも時間がかかります。
自分では当たり前のように思っていても、引き継ぐ人にとっては分からないことが多く不安を感じてしまうものです。
業務に関係する備品がどこにあるのか、細部まで引き継ぎをすることが求められます。
しかし引き継ぎと繁忙期が重なってしまうと、十分な引き継ぎは出来ません。
自分自身も大変ですが、引き継ぐ相手も大変です。
結果、退職後に業務連絡が入ってしまうでしょう。
退職時期はタイミングが大切です。
繫忙期はなるべく避けて、十分な引き継ぎの時間を取りましょう。
退職時の不明点は早めに確認しよう

退職に慣れている人はあまりいないはずです。
退職時に何をすべきか、不明な点は早めに解決しておくことがポイントです。
一般的には2ヶ月ほど前には退職の意思を伝え、上司などに相談をして詳しい退職日を決めます。
引き継ぎを行う際は、関係各所に退職の挨拶をして回ることになるでしょう。
並行して退職手続きも行っていきますが、企業から受け取る物と企業へ返却すべき物をリストアップしておくと漏れがないのではないでしょうか。
必要書類に関しては記入ミスを防ぐ為にも、何をどのように記入すればいいのか事前にしっかり調べておきます。
退職に関する不明な点、手順なども転職エージェントに相談してはいかがでしょう。
後にトラブルにならないように、気持ちよく退職準備をしたいものです。
退職までにやっておくべきことをチェック

次に退職までにやっておくべきことを細かく確認していきます。
転職者の場合は特に、次の生活へ気持ちが向きがちですが退職日まで気を引き締めていきましょう。
退職スケジュールを作成しよう
スムーズな退職を行う為にも、退職を決意したら退職スケジュールを作っておくべきです。
この時企業側の都合なども念頭に入れて、退職までの流れをイメージし書き出してみることをおすすめします。
また企業側に退職の意志を伝える際には、一度就業規則などを確認しておくといいのではないでしょうか。
いつまでに何を完了する、必要な書類はいつまでに揃えるなど、細かくスケジュールを立てます。
自分のスケジュール通りに進めば問題はないのですが、思うように進まない時もあるものです。
退職スケジュールは余裕をもって、すべきことをリストアップしておきましょう。
また、引き継ぎをする人材を早期で決めておくことも大切です。
上司との相談になるかと思いますが、意外に時間がかかってしまい引き継ぎがギリギリになってしまった、という人も多いようです。
引き継ぎをする人材の確保は、積極的に進めていきましょう。
業務の引き継ぎノートを作成しよう

引き継ぎは口頭だけではなく、ノートなどに残しておくと理解しやすいです。
引き継ぐ相手の気持ちになって、分かりやすくまとめておきましょう。
ノートを見れば問題が解決するように引き継ぎノートを作成しておけば、退職後に連絡が来ることもなくなるのではないでしょうか。
もしも自分が仕事を引き継ぐならば、何を知りたいかを考え後任へ引き継いでいきます。
業務内容だけではなく、これまでのトラブル対処方法なども付け加えておくと引き継ぎ後の役に立ちます。
退職3日前には引き継ぎを完了させよう
引き継ぎを行う際は、目安として退職日の3日前には全て完了しておくといいでしょう。
全てを引き継いだと思っていても、質問が残っていたり思わぬところに引き継ぎミスが発生したりするものです。
また引き継ぎは通常業務と並行して行われる為、自分が立てたスケジュール通りにはいかないものです。
退職3日前には引き継ぎの完了を目指し、その後は質問や補充の時間を取ると親切でスムーズな引き継ぎが出来るのではないでしょうか。
退職時に返却するものは事前にチェックしておこう

退職後の業務連絡で多いものの一つに、企業への返却物があります。
返却を忘れると、後日連絡が来るばかりか手間にもなってしまうのでしっかりと事前にチェックしておきましょう。
健康保険被保険者証
加入している場合は忘れずに返却しましょう。
自分が扶養している人物がいたら、その人の分まで返却する必要があります。
すぐに次の転職先へ移行するのなら、転職先で健康保険被保険者証を発行してもらえるでしょう。
それ以外は、却後に国民健康保険へ加入したり、家族の扶養になったりします。
また2ヶ月以上社会保険に入っているなど、一定の条件を満たしていれば健康保険を任意で継続することも可能です。
社員証などの身分証明書

仕事で使用していた身分証は返却を忘れると、大事になってしまう可能性もあるので必ず返却しましょう。
企業側としてもセキュリティ面で気を使う返却物です。
忘れてしまいがちなのが、他企業での入館証などになります。
社員として支給された身分証は全て返却の対象となり、紛失時には補償の問題になることもあるので気をつけましょう。
自分と取引先の名刺
上記しましたが、自分の名刺は勿論のこと取引先の名刺も全て返却することになります。
取引先の顧客はあくまでも企業の財産です。
同業種や同職種に転職する際に、これらの情報を利用することは損害賠償などに発展する危険性もあります。
つい返却を忘れてしまった、ということのないように事前にしっかりとまとめておきたいものです。
この他にも通勤用の定期券(交通費が出ている場合)や備品など返却漏れがないようにしっかりチェックしておきましょう。
退職後のトラブル事例を確認しよう

退職後は出来る限りトラブルを避けたいものですが、自分の思いもよらぬ所からトラブルが発生することもあります。
退職後の悩みの種になる事柄を紹介します。
業務上のトラブル
退職後ことあるごとに業務についての質問の連絡が来る、と悩んでいる人は多いようです。
業務の引き継ぎは自分の責任でもある、と感じ対応していても度が過ぎる質問などには頭を悩ませてしまいます。
中には調べれば分かること、社内の人間でも分かることまで質問してくる場合があるようです。
法的に対応する義務はないので、あまりにも度が過ぎるようであれば対応出来ない旨をしっかりと伝えることも検討してはいかがでしょう。
また、後任の人の仕事への不安を事前に消しておくためにも、入念な引き継ぎをしておきたいものです。
人間関係のトラブル
女性の場合、退職後に上司や同僚から執拗な連絡が来ることもあります。
在職中に言えなかったことでも、退職を機に連絡をしてくる人もいるようです。
対応に困る連絡ですが、今後関係を切っても問題ない相手だったり、自分が不快な思いをしたりするのであれば、対応をしない決断をしましょう。
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
トラブル回避のポイントやトラブルが発生した場合は

退職後のトラブルを未然に防ぐには、企業への返却物をもれなく返却出来るように前もってリストを作っておきましょう。
また最も多い引き継ぎ後の質問連絡については、しっかりと引き継ぎノートを作成し、余裕を持って引き継ぎを済ませておきます。
更に業務ごとに社内の誰が詳しいのか、など引き継ぎの際に付け加えておくといいかもしれません。
トラブルが発生してしまった場合は、退職前の上司へ相談してもいいのではないでしょうか。
個人的な連絡についてなどは対応しないという方法もあります。
更に企業側とのトラブルが発生した時は、労働基準監督署などに相談することをおすすめします。
転職の相談は転職エージェントを活用しよう

退職は簡単なようで、見落としがちな手続きが多くトラブルが頻繁に発生するものです。
事前の準備がスムーズな退職の鍵となります。
しかし詳しい退職手続きの方法や、健康保険の手続きなど少々専門的な知識を必要とするケースもあります。
転職エージェントは退職の際の手続きなどにも相談にのってくれます。
トラブルを避けるためにも、転職エージェントに相談して退職を進めていってはいかがでしょうか。
まとめ
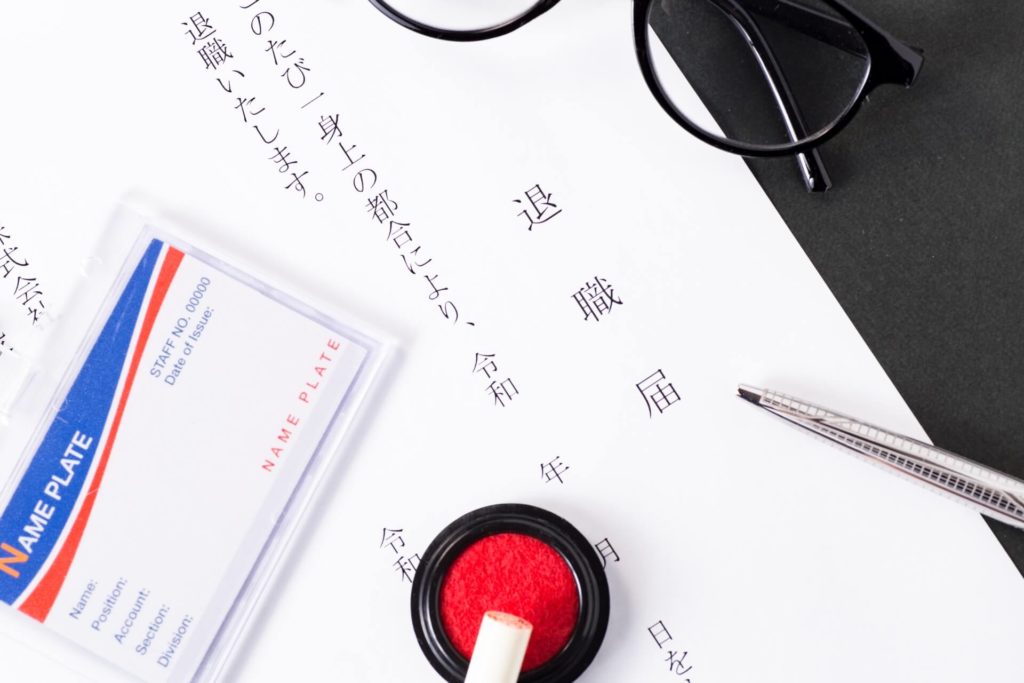
退職後の業務連絡は、多くの退職者が経験しています。
これまで自分が携わってきた多くの業務を引き継ぐので、多少の引き継ぎミスが生じることもあります。
退職後の業務連絡については、本人の考え方によるともいえるでしょう。
少しでも退職後の業務連絡を減らせるように、退職スケジュールを細かく立てていきたいものです。
転職成功への近道は自分にあった転職サイトを見つけること!
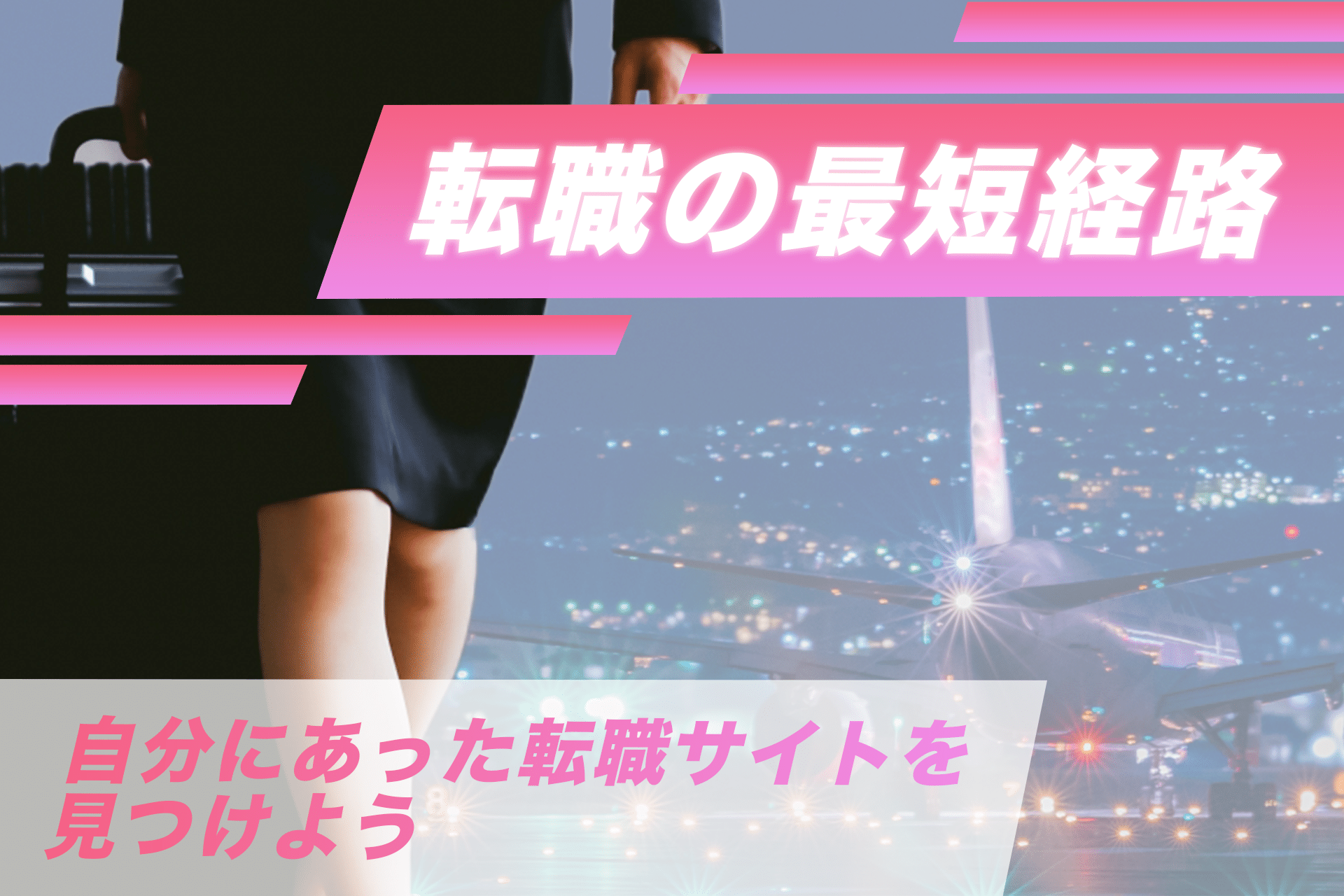
転職サイトはそれぞれ特徴や強みが異なります。
そのため、転職成功には自分の目的や希望職種にあった転職サイトを見つけなければなりません。
- 種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない
- 自分にあった転職サイトはどうやって見つければいいの?
こんな悩みをお持ちではないですか?
以下に転職サイトの選び方と比較を紹介します。
是非参考にしてみてください!
転職サイトの選び方
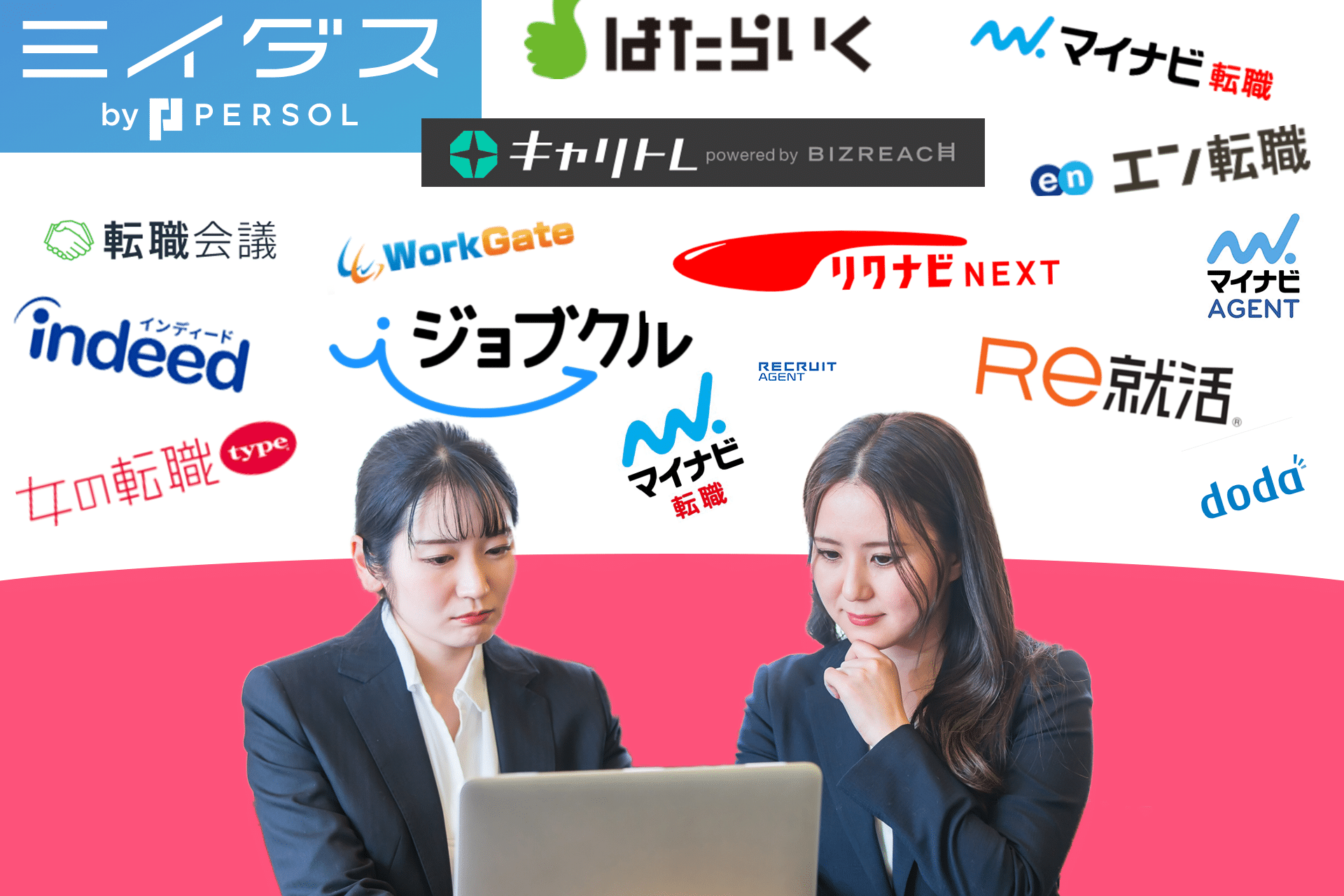
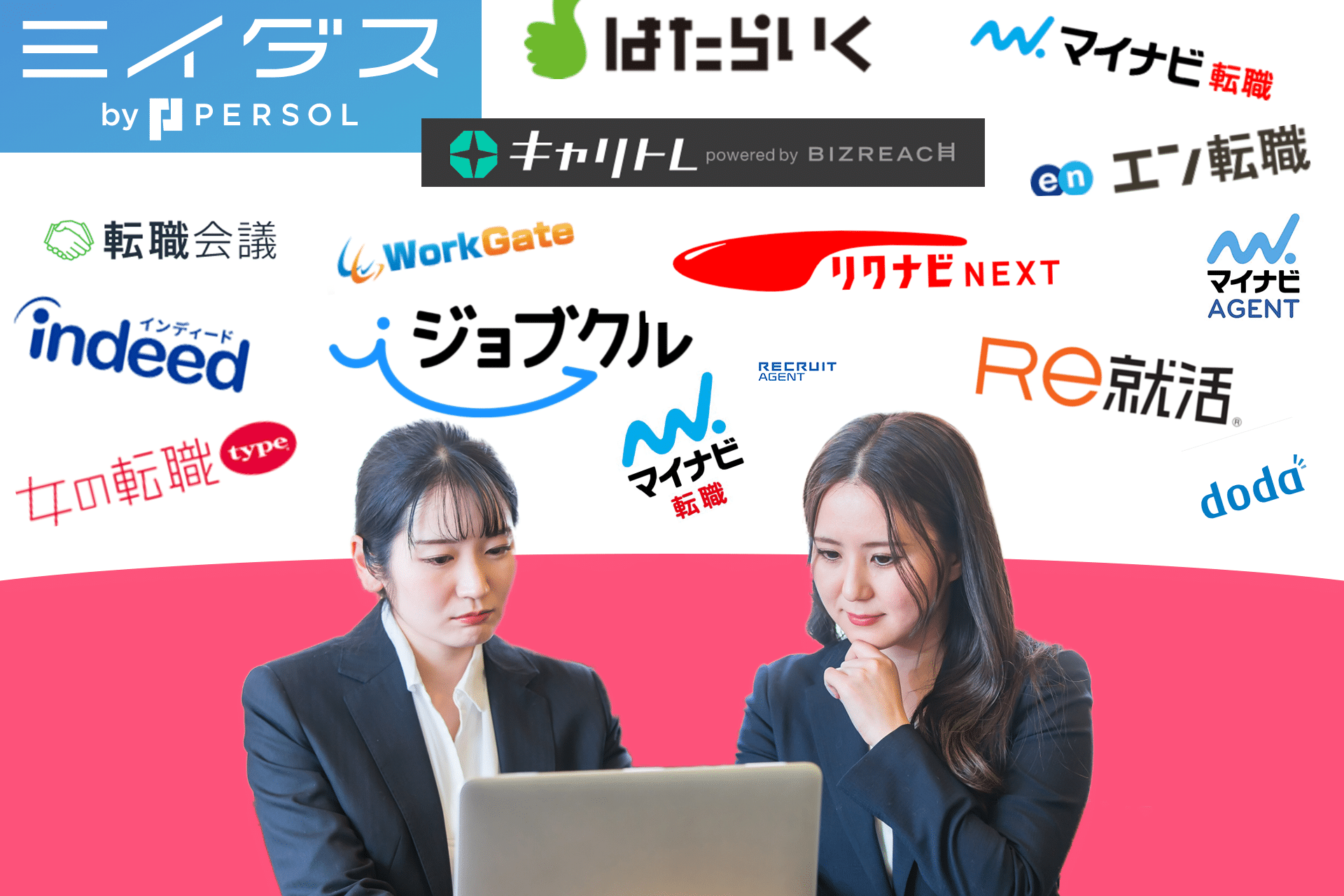
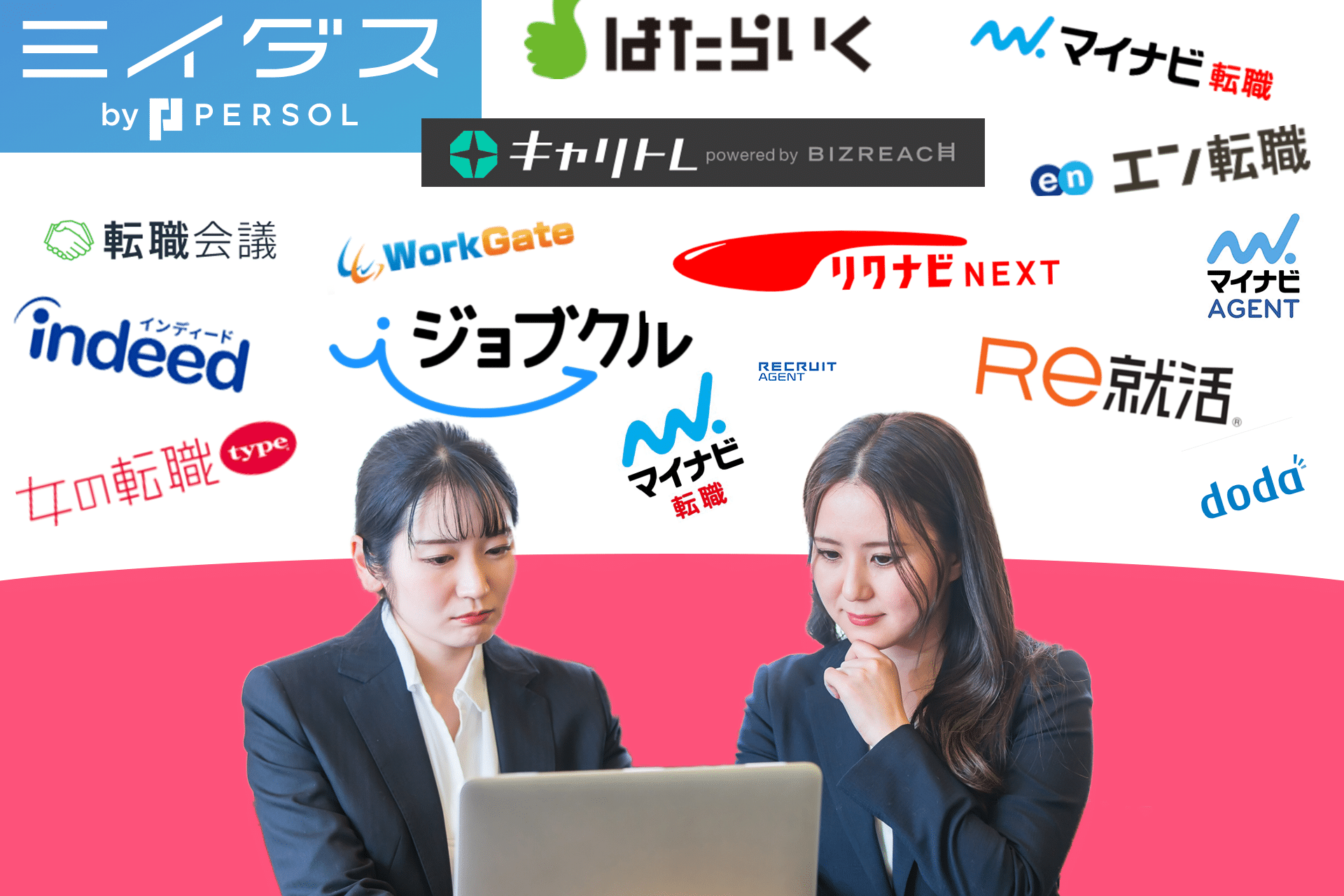
転職サイトは以下のような進め方で選ぶと最適なものを選ぶことができます。
- 「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
- 転職目的や職種など希望から選ぶ
これらをより詳しく見ていきましょう。
「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
転職サイトは大きく分けて2種類存在します。
- エージェント型:担当のキャリアアドバイザーがついて転職活動のサポートをしてくれる
- サイト(求人広告)型:求人広告が掲載されており、自身で転職活動を進める
それぞれメリット・デメリットはありますが、転職の成功率を上げるのであれば使い分けが重要です。
各サイトで扱っている求人も異なりますので少し面倒かと思っても満足のいく転職をするために使用してみてください。
転職目的や職種など希望から選ぶ
すでに転職の目的が定まっている人もいることでしょう。
そんな方は「第二新卒の活躍を支援しているサイト」や「IT業界に特化したサイト」など、幅広い支援をしてくれる大手サイトだけでなく目的にあったサイトも活用するとより満足のいく転職ができます。
おすすめ転職エージェントBEST3



ウィメンズワークスが厳選した転職エージェントをご紹介します。
転職エージェントの特徴は求人数が多いことです。
そのため、幅広いがゆえに初めての転職やどの転職エージェントを使ったらいいかわからないこともあるでしょう。
そんな方は是非参考にしてみてください。
1位.マイナビAGENT
マイナビAGENTは20代・30代の転職に強い転職エージェントです。
担当者が親身になって応募書類の準備から面接対策まで転職をサポートしてくれるので、初めて転職する方でも安心です。
第二新卒のサポートも手厚く企業担当のアドバイザーが在籍しているため、職場の雰囲気や求人票に載っていない情報を知ることができます。
転職先でうまくやっていけるか不安な方や初めての転職にはマイナビAGENTがおすすめです。
マイナビエージェントの詳細はこちら
マイナビAGENTの評判はこちら
2位.dodaエージェント



dodaエージェントは、幅広い業界や業種の求人を取り扱う国内最大級の転職エージェントです。
dodaのみが取り扱っている求人も多く、転職活動の視野を広げたい方におすすめです。
また、応募書類のアドバイスや書類だけでは伝わらない人柄や志向などを企業に伝えてくれたり、面接前後のサポートも手厚いです。
dodaエージェントは、20代30代だけでなく地方での転職の方にもおすすめできる転職エージェントです。
3位.リクルートエージェント
リクルートエージェントは多数求人を保有している、転職支援実績No.1の総合転職エージェントです。
一般公開求人だけでなく、非公開求人数も10万件以上取り揃えています。
転職において求人数が多く実績も豊富なため、必ず登録すべき1社と言えます。
また、各業界・各職種に精通したキャリアアドバイザーがフルサポートしてくれるため、初めての転職でも利用しやすいでしょう。
リクルートエージェントの詳細はこちら
リクルートエージェントの評判はこちら
おすすめ転職サイトBEST3



先述した通り、転職エージェントは求人が多いです。
しかし、エージェントに登録していない企業もあります。
転職は「情報をどれだけ集められるか」が非常に重要になります。
そのため、転職エージェントだけでなく転職サイトもぜひ活用していきましょう。
ウィメンズワークスが厳選した転職サイトをご紹介します。
1位.doda



dodaはリクナビNEXTに次いで多くの求人数を保有しており、利用者満足度の高い転職サイトです。
お気づきの方もいるかとおもいますが、dodaは転職エージェントと一体型なのです。
つまり、dodaに登録することで求人を見ることも、転職エージェントに相談することも出来ます。
情報収集をしつつ気になった企業への相談がすぐにできるので非常に魅力的な転職サイトと言えるでしょう。
転職初心者はリクナビNEXTと合わせて登録しておくことがおすすめです。
2位.マイナビ転職



マイナビ転職は、大手人材企業「マイナビ」が運営する転職サイトです。
20代〜30代前半に多く利用されている若者向け転職サイトで、若手を採用したい企業が多いので第二新卒や20代であれば転職成功に大きく近づけるでしょう。
また独占求人が多く、他サイトにない求人に巡り合うことができるのでこちらも登録することをおすすめします。
20代〜30代前半であれば登録しつつ他サイトと比較していくと選択肢が広がるきっかけになるでしょう。
マイナビエージェントの詳細はこちら
マイナビ転職の評判はこちら
3位.リクナビNEXT



リクナビNEXTは、大手人材企業「リクルート」が運営する、業界最大規模の転職サイトです。
転職をする際はまず登録すべきサイトの一つです。
リクナビNEXTの掲載求人は20代~50代までと幅広く、地域に偏らないことも大きなメリットです。
リクナビNEXTであれば希望条件に合致する求人や地方在住に関わらず、自分に合う仕事が見つかるでしょう。
また、「グッドポイント診断」を使用すれば自分では気が付かない長所や強みを見つけるきっかけになります。
これらを活用して書類作成や面接準備もスムーズに進めることができるでしょう。
リクナビNEXTの詳細はこちら
リクナビNEXTの評判はこちら
まずは派遣!そんな考えのあなたに



まずは派遣で自由に好きな仕事をしたいと思う方も多くいます。
自分にあったお仕事探しをしたい方はなるべく大手の派遣会社に登録するのが良いでしょう。
でもどの派遣会社にしたらいいかわからない…。
そんな方のためにウィメンズワークスが厳選した派遣会社をご紹介します。
1位.テンプスタッフ



テンプスタッフは日本全国に拠点が有りどの地域に住んでいても派遣の仕事が紹介されることが魅力です。
業界最大級の求人数で、幅広い業界や職種からあなたにピッタリの仕事が見つかるでしょう。
中でも事務職の求人が多く、事務職になりたい方は必ず登録しておきたい派遣会社です。
2位.アデコ



アデコは有名・優良企業の求人が多数で「今後もこの派遣会社から働きたい(再就業率)」No.1を獲得しています。
有名・優良企業の求人が多いので大手で安心して働ける環境が整っています。
わがまま条件を叶えたい方、幅広い求人から自分にあった仕事を探したい方におすすめの派遣会社です。
3位.パソナ



パソナは高時給・大手上場企業の求人が多数揃っています。
パソナは派遣会社にもかからわず月給制を取り入れており、安定的に収入を得ることができるでしょう。
更に福利厚生が充実しており、安心して派遣のお仕事に取り込んでいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。
これまでのスキルを活かして高単価で仕事を探したい方におすすめの派遣会社です。

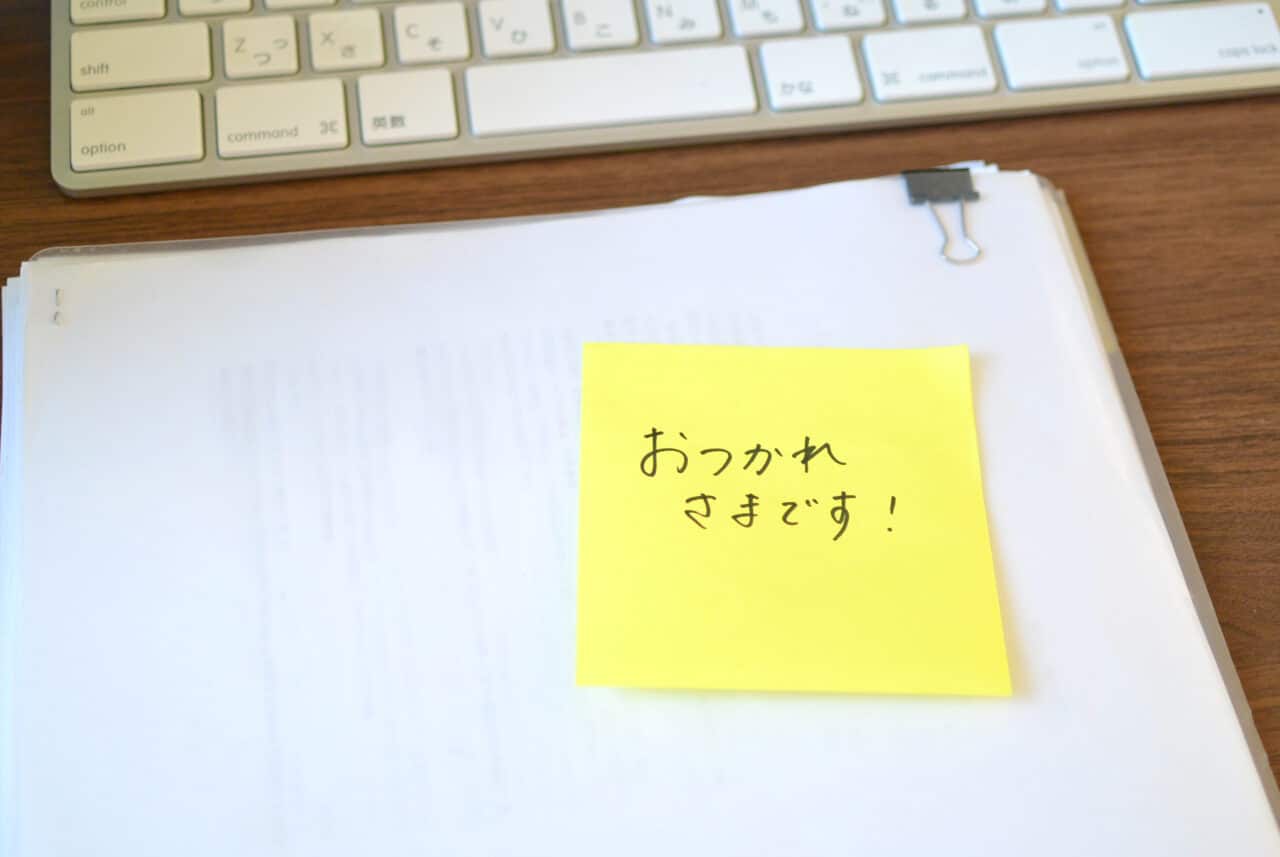
 LINEで送る
LINEで送る


