退職をするにあたり、しっかりと手続きをするうえで、退職届の準備は欠かせません。
またビジネス文書であることを考えると、用紙や封筒もマナーにそったものを選ぶべきでしょう。
そこで今回は、退職届に必要な用紙や封筒はコンビニで買えるのか、マナーを守った準備方法について解説します。
Contents
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
退職を決めたら退職届を用意しよう

会社を退職すると決めたら、まずは直属の上司に口頭でその意思を伝えるのが基本です。その後に退職届を提出するのが慣例です。
日本の法律では口頭であっても、退職の意思を示してから14日を経過すると、雇用契約は終了すると見なされます。
しかし、退職にあたって会社とトラブルになると、必要書類を用意してもらえないなどの弊害が出ることもあり注意が必要です。
退職にあたってはしっかりと手順を守り、退職届は用意しておきましょう。
退職願いと退職届は何が違うの?
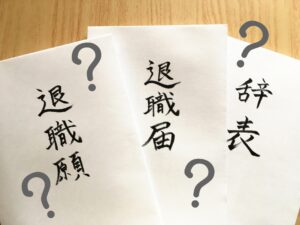
初めて会社を辞めようとしている人の中には、退職願いと退職届を混同している人もいるかもしれません。
しかしこの二つの書類は、内容も提出するタイミングも異なります。
退職願いとは、会社に対して自分の退職の意向を伝え打診をするために提出する書類です。
上司に口頭で退職を申し出る場合は、退職願いを提出しないことも珍しくありません。
退職願いはあくまでも、退職の意思を伝えるためのものであり、会社側が承諾するまで取り下げることが可能です。
一方の退職届は会社に退職が了承された際に、退職の意思を明確に伝えるための書類をさします。
そして退職届は、会社の承諾の可否を問わずに提出できる書類です。そのため、法律上は退職届を提出した日から2週間後に退職できます。
口頭のやりとりだけではトラブルに発展した際に証明ができないこともあり、記録に残す意味でも退職届の提出は一般的に行います。
そして退職届を提出すると、撤回はできないのが原則ですが、退職届を取り下げる旨を会社側が了承すれば、残ることは可能です。
しかし、退職届の撤回を認めるかどうかは会社の判断になるため、提出にあたっては熟考することをおすすめします。
退職届に必要なものはコンビニで揃う?

退職届を作成するにあたり、便せんや封筒を用意する必要がありますが、サイズ並びに色柄などへの配慮することも大切です。
また退職届に必要なものをわざわざ、文房具店に買いに行くのが難しいこともあるでしょう。
ここでは、退職届に必要なものはコンビニで揃うのかについて紹介します。
用紙は?

退職届に使用する用紙は、コピー用紙もしくは白い便箋が基本で、どちらもコンビニで購入可能です。
一般的なコピー用紙は、セブン-イレブンやファミリーマートで購入できます。
白い便箋はコクヨの縦書きがおすすめですが、セブン-イレブンやローソン、ファミリーマートなど大手コンビニで取り扱っています。
封筒は?
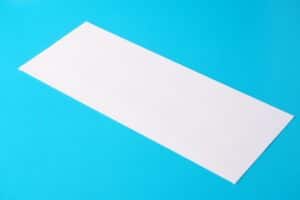
退職届は折りたたんで封筒に入れて提出するものですが、白封筒を選ぶのが慣例となっています。
その際には封筒のサイズは長形4号、長形3号のいずれかを選ぶのですが、選び方のポイントは後述します。
長形4号または長形3号の白封筒は、ローソンまたはファミリーマートで購入可能です。
それ以外に購入できる場所
退職届に必要な用紙や封筒は、コンビニ以外でも買うことができます。
文房具店だけでなく、ダイソーやセリアといった100円ショップでも販売されています。
中でもセリアでは、様々なサイズのコピー用紙が販売されているので便利です。
書き直すことを想定し、多めに用意しましょう。
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
退職届に適した用紙サイズは
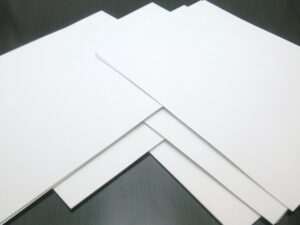
退職届にはA4版またはB5版の用紙を使うのが慣例となっていますが、どちらを選んでも問題ありません。
退職届はA4版が一般的と紹介している転職サイトなども多いですが、B5版は封筒に入れた後スーツのポケットにしまいやすいです。
白いコピー用紙に退職届の文章をプリントしようと考えているなら、自宅に常備されていることが多いA4版でかまいません。
手持ちの封筒をチェックして、適応するサイズの用紙を選びましょう。
退職届に適した用紙は

退職届は会社に提出するビジネス文書ですので、適した用紙を選ぶのがマナーです。
ここでは、退職届に適した用紙とはどんなものかを説明します。
白い紙が定番
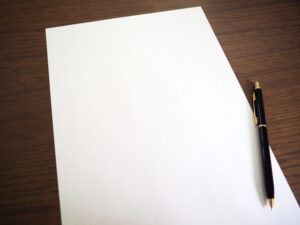
退職届に用いる用紙は白い紙であることが定番となっており、基本的には白いコピー用紙または白い便箋を使います。
コピー用紙の中には再生紙や色付きのものもありますが、退職届には適していないので、使わないようにしましょう。
罫線入りの便箋でもOK

一方の便箋を使うときには白地に細く黒い罫線が入っているだけの、シンプルなものを選ぶのがマナーです。
色や柄、イラストが入った便箋はもちろん、凹凸のある和紙などもマナー違反になりますので、選ばないようにしましょう。
指定の用紙があればそれを使おう

また企業によっては、会社で退職届の書式を用意しているところもあります。その場合は、総務部や人事部などから受け取りましょう。
また近年は、退職届専用用紙がamazonなどで販売されています。専用用紙には書き方や注意事項が書かれているので便利です。
専用用紙は縦書きと横書きの2種類があるので、どちらがよいかを判断しましょう。
退職届を入れる封筒は

退職届は郵便番号枠のない白い封筒に入れて提出するものですが、折り方にもマナーがあり、適したサイズを選ぶことが大事です。
ここでは、退職届を入れる封筒について説明します。
紙に合わせたサイズを選ぶ
退職届は折りたたんで、封筒に入れて提出するものです。だからこそ、用紙に合わせたサイズを選ぶ必要があります。
退職届に適した用紙はA4版またはB5版ですので、封筒もそれに合うサイズを選びます。
A4版の用紙サイズは210×297㎜なので、大きさが120×235㎜となっている長形3号を選びましょう。
B5版の紙サイズは182×257㎜なので、大きさが90×205㎜の長形4号がおすすめです。
色は白がベスト

退職届はビジネス文書ですので、色は白がベストです。白であっても凹凸や透かし模様が入った封筒は、退職届には合いません。
さらに退職届には、二重封筒がおすすめです。二重封筒であれば、中味が透けて見えることがないからです。
のり付きの封筒の場合はマナーとして、封をして〆マークを書いて提出しましょう。
郵便番号欄はいらない
白い封筒の中には、赤い郵便番号枠が印刷されているものもありますが、退職届に使用するのは郵便番号の枠がないものにしましょう。
これは無地の白封筒には清潔感があり、フォーマルとされているからです。
退職届の折り方は
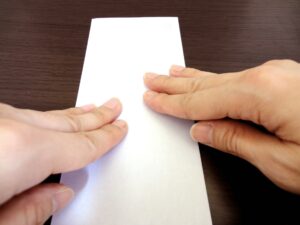
白封筒に退職届を入れるときには、折り方にもマナーがあります。開いた時に読みやすいよう、三つ折りにするのがマナーです。
三つ折りのやり方は、以下の通りです。
・きれいなテーブルに、用紙をまっすぐに置く
・用紙の下3分の1を上に向かって折り返す
・上の3分の1を下に向かって折り返す
三つ折りにした退職届は、書き出しである右上が裏返した封筒の右上にくるように入れるのがマナーです。
そして封筒に退職届を入れるときには、しわにならないように丁寧に入れてください。
万が一、三つ折りにした退職届が手元にある封筒に入らない場合は、四つ折りにしてもマナー違反にはなりません。
封筒から出したときにしわにならないように、どちらかの折り方を選択しましょう。
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
退職届の書き方

そのため退職届を提出するにあたり、手書きとパソコン作成のどちらがよいのか、迷う人も多いことでしょう。
ここでは、退職届の書き方のマナーについて説明します。
手書き?パソコン?
退職届は、原則的には手書きとされ、その場合は黒いボールペンか万年筆を使って書くのがマナーです。
しかし近年は、パソコンで作成するケースも増えています。効率重視の外資系企業やベンチャー企業には、特に多いようです。
社風にもよりますが、基本的には手書きすることをおすすめします。特に年配の上司に提出する場合は、手書きの方が無難です。
しかし、勤務先からパソコンで作成するよう指示されるケースもあるので、会社のフォーマットをまず確認しましょう。
縦書き?横書き?

退職届を作成するにあたり、縦書きにすべきか、横書きでもよいのか、迷う人もいることでしょう。
基本的には、退職届は縦書きで手書きするものと覚えておきましょう。
しかし近年は、企業名にアルファベットが使われているケースも多く、その場合は横書きの方が書きやすいです。
退職届を提出する際に、会社の人事部または総務部で確認することをおすすめします。
会社都合で辞める際にも退職届は必要?
本来の退職届は、従業員が自分の意思を伝えるためにある書類です。
しかし退職の事務処理をするにあたって、会社都合であっても退職届を提出するよう求めるところもあります。
会社都合で退職するときには事前に人事に問い合わせたり、就業規則を確認することで、退職届が必要か否かを確認しましょう。
また、会社都合で退職する際には文面の中に具体的な退職理由を書くことが、とても大切です。
書かれている退職理由によって、失業保険の受給時期が変わる可能性があるからです。具体的な書き方は、次章で説明します。
書くべき内容は?
退職届は書き方や書くべき内容が決まっているので、マニュアル通りに書くようにしましょう。具体的な内容を以下にまとめます。
・冒頭行:「退職届」と記載する
・導入文:自己都合退職の際には「このたび一身上の都合により」と記載する
会社都合の際には、「部門縮小のため」「退職勧奨に伴い」「早期退職のため」などの文言を入れる
・退職日付:上司と退職の合意が得られた年月日を書くのが基本。西暦でも元号でもかまわないが、会社規定を確認するのがおすすめ
・文末表記:退職届の場合は「退職いたします」と明記する
・届出年月日:書類を提出する日付を記載する
・所属部署と氏名:行の下になる位置に、所属部署の正式名称とフルネームを記載し、捺印する
・宛名:会社の再校進行責任者が基本なので、社長の名称を入れる。行の上段に役職とフルネームを記載し、殿あるいは様をつける
書くべき内容は、縦書きでも横書きでも変わりません。しかし文章の配置など、書き方は違うので下調べをしましょう。
手渡し?郵送?
会社に在籍中に退職届を提出するときには、上司や担当部署の人に手渡しするのがセオリーです。
しかしケガや病気で休職している、または本社が遠く手渡しするのが難しいこともあるでしょう。
中には、会社が退職届の受け取りを拒否するケースもあります。そうした事情で手渡しが難しい場合には、郵送してかまいません。
ただしその場合は、退職届が料金不足で返送されることを防ぐためにも、郵便局の窓口から送ることをおすすめします。
また、郵送した退職届が届いていないと主張されることを防ぐために、内容証明郵便として送る方が安心です。
合わせて退職時のトラブルを避けるため、退職届を郵送して終わりではなく、会社とは連絡を取るよう心がけましょう。
退職トラブルがあると転職活動にマイナスになる可能性が高まるので、誠意をもって対応するのがおすすめです。
退職届を入れる封筒の書き方

退職届は用紙がしわにならないだけでなく、封筒もきれいな状態で提出するのがマナーです。
そして退職届を入れる封筒の書き方も、マナーを守ることが大事です。
ここでは、退職届を入れる封筒をマナーを守って書く方法を具体的に紹介します。
表面に書くこと
白い封筒の表面には、楷書で「退職届」と書きましょう。前述した通り、黒いインクのボールペンまたは万年筆で書きます。
「退職届」の文字は縦書きが基本で、封筒の中央より上の部分に大きめの文字で書き、企業名などは入れる必要はありません。
万が一、書き損じをしてしまったときには修正するのではなく、別な封筒に書き直しましょう。
裏面に書くこと
退職届を入れた封筒の裏面には、自分の所属部署とフルネームを書きます。書く場所は封筒裏面の左下です。
裏面の文字は表面のように大きくなくてかまいません。封をする場合は、〆マークを書くのを忘れないようにしましょう。
郵送する場合の書き方
退職届を郵送するときには、退職届の入った長形4号封筒を、長形3号封筒に入れて送るのがセオリーです。
長形3号封筒には、会社の住所と会社並びに部署名、そして開封してほしい人の個人名を書きます。
中小企業であれば社長名でかまいませんが、大企業の場合は人事部の役職者や直属の上司が宛名になるケースもあるようです。
そして封筒の表面の左下に、朱書きで「親展」と記載して赤い罫線で囲みます。
「親展」という言葉には、宛名本人しか開封しないようにという意味が込められているからです。
裏面には自分の住所とフルネームを書き、しっかり〆マークも入れましょう。
まとめ

今回は、退職届の紙はコンビニで買えるのかをはじめ、書き方や折り方、サイズなども含めたマナーについても解説しました。
円満退職してから転職するにこしたことはありませんので、退職届はマナーを守って作成するのが大人のたしなみです。
用紙や封筒はコンビニでも入手可能ですので、サイズ選びや書き方にも配慮して作成しましょう。
転職成功への近道は自分にあった転職サイトを見つけること!
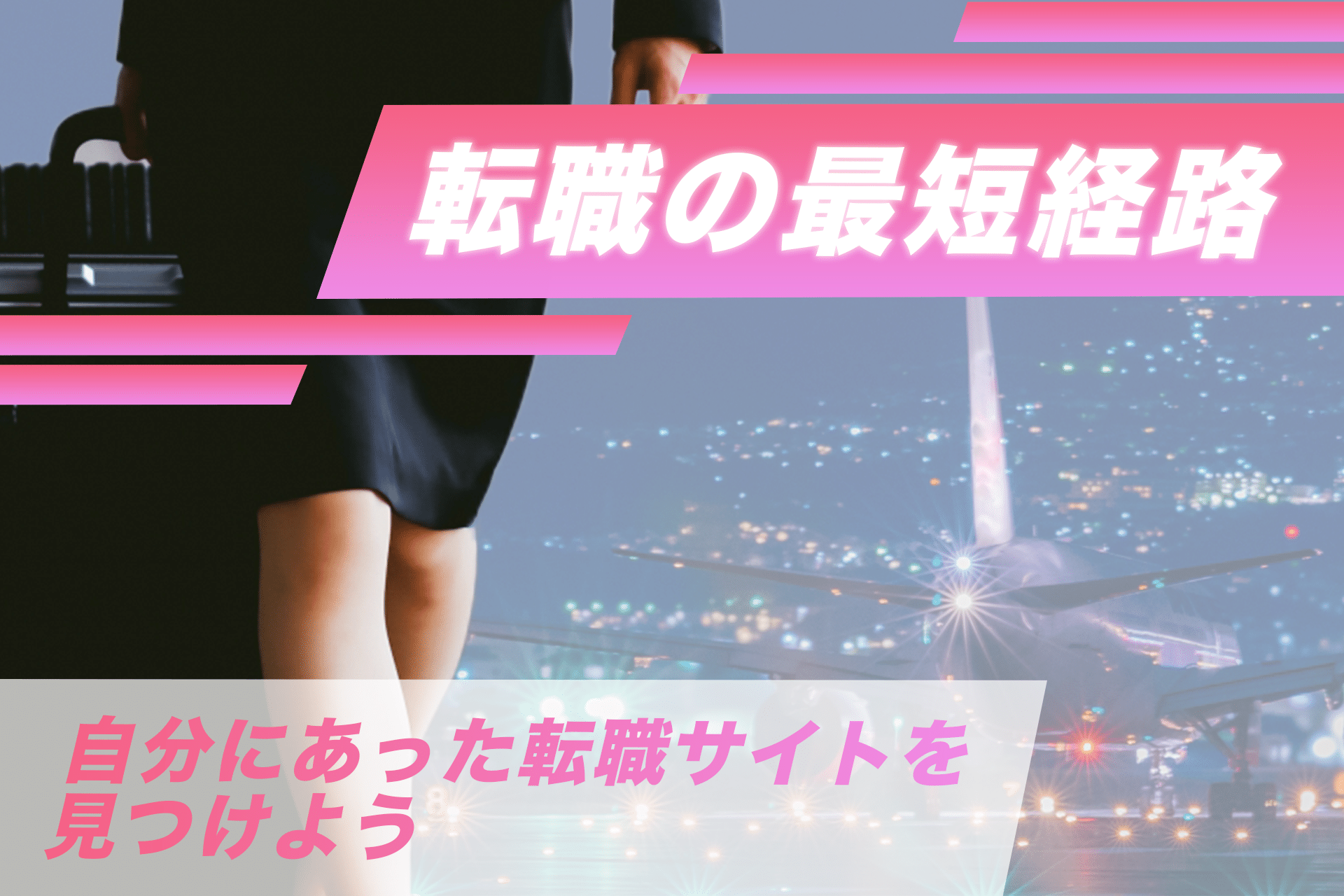
転職サイトはそれぞれ特徴や強みが異なります。
そのため、転職成功には自分の目的や希望職種にあった転職サイトを見つけなければなりません。
- 種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない
- 自分にあった転職サイトはどうやって見つければいいの?
こんな悩みをお持ちではないですか?
以下に転職サイトの選び方と比較を紹介します。
是非参考にしてみてください!
転職サイトの選び方
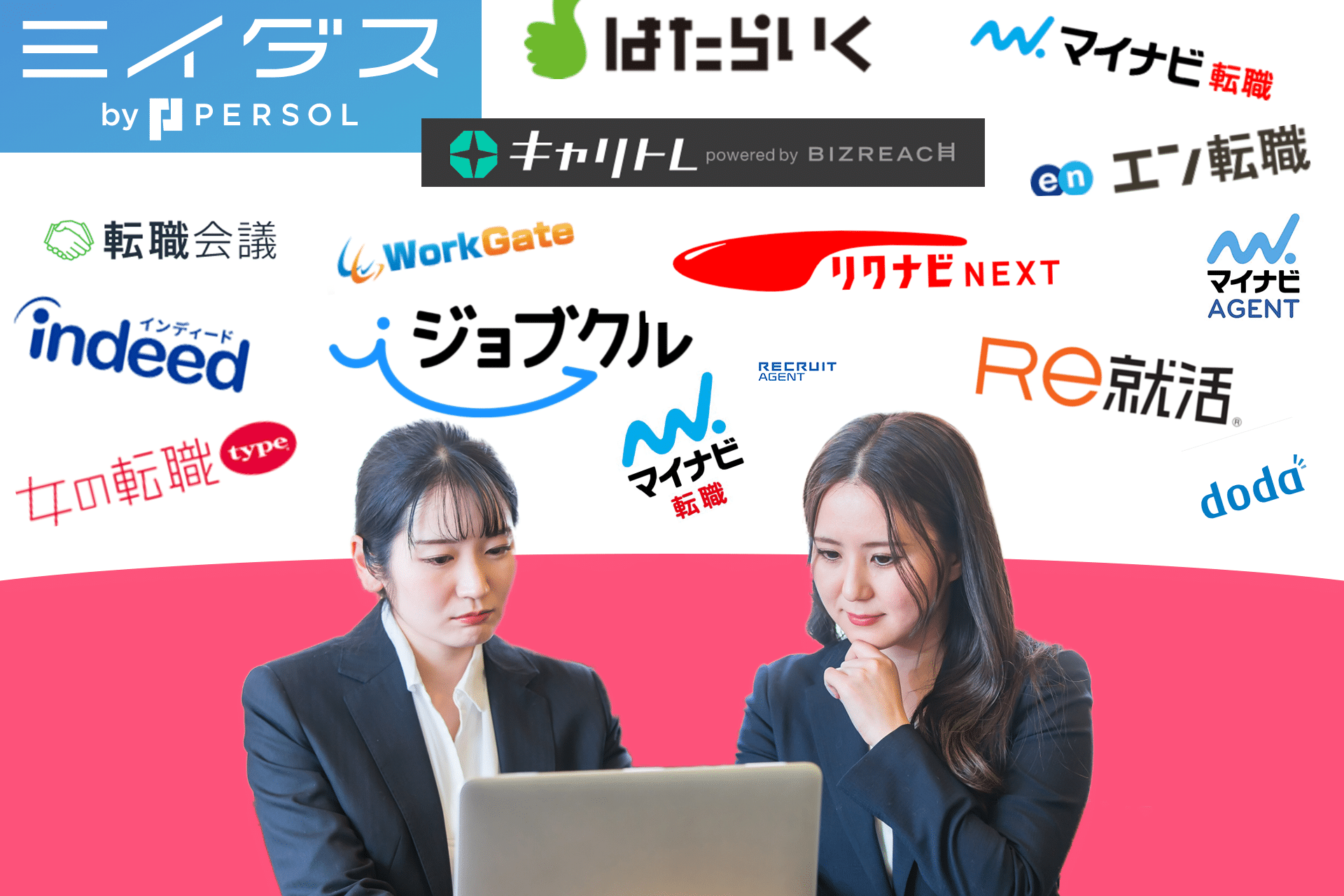
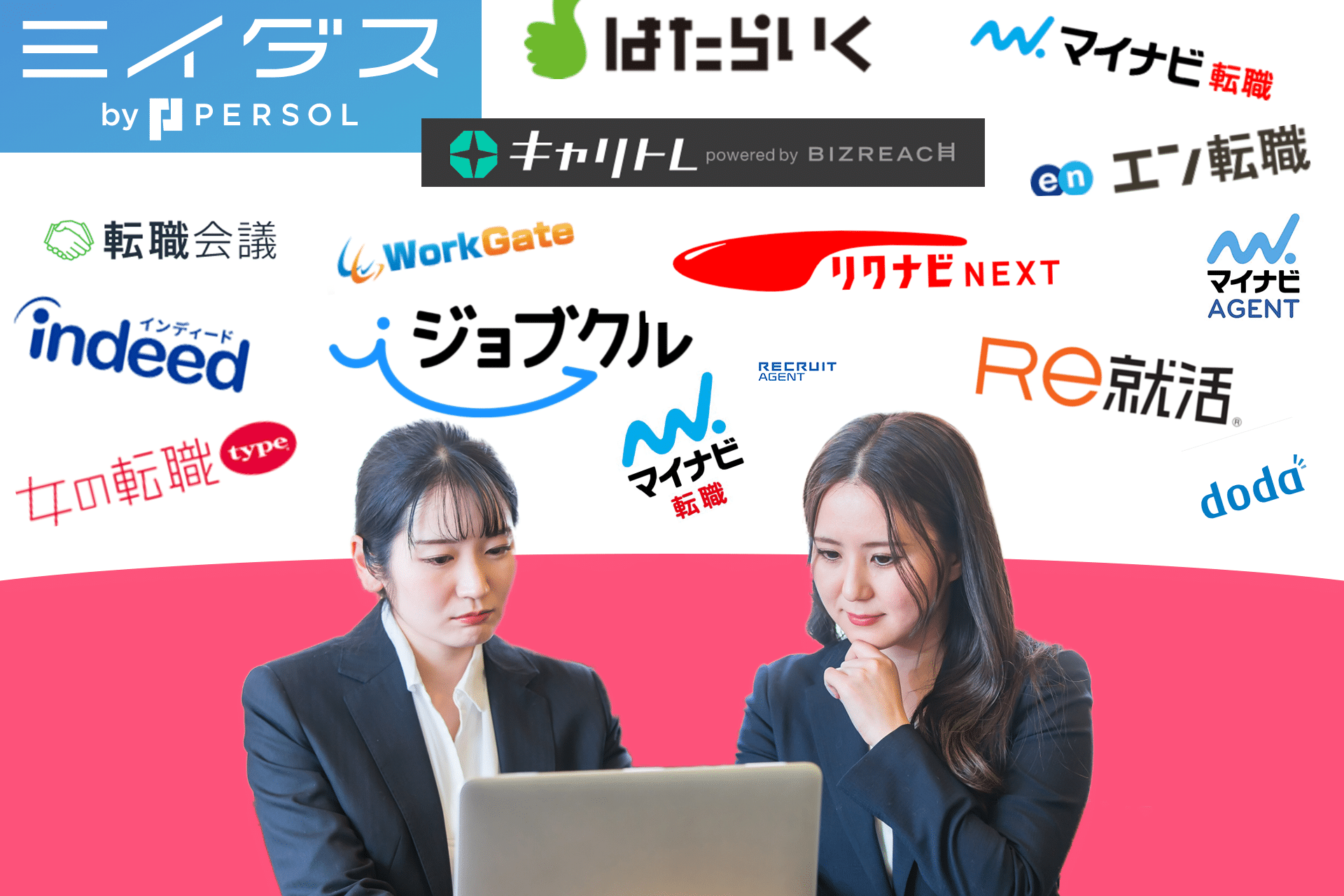
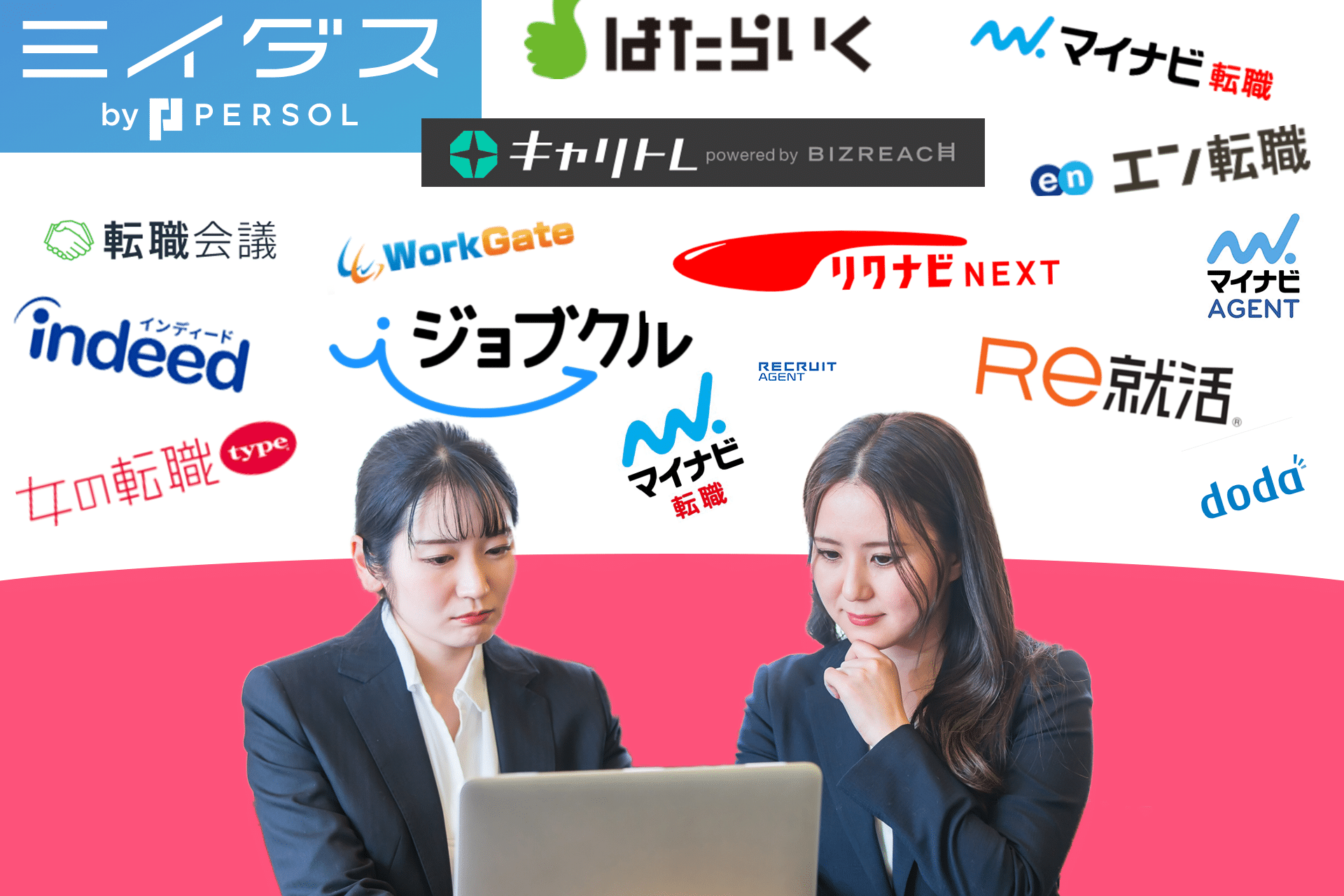
転職サイトは以下のような進め方で選ぶと最適なものを選ぶことができます。
- 「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
- 転職目的や職種など希望から選ぶ
これらをより詳しく見ていきましょう。
「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
転職サイトは大きく分けて2種類存在します。
- エージェント型:担当のキャリアアドバイザーがついて転職活動のサポートをしてくれる
- サイト(求人広告)型:求人広告が掲載されており、自身で転職活動を進める
それぞれメリット・デメリットはありますが、転職の成功率を上げるのであれば使い分けが重要です。
各サイトで扱っている求人も異なりますので少し面倒かと思っても満足のいく転職をするために使用してみてください。
転職目的や職種など希望から選ぶ
すでに転職の目的が定まっている人もいることでしょう。
そんな方は「第二新卒の活躍を支援しているサイト」や「IT業界に特化したサイト」など、幅広い支援をしてくれる大手サイトだけでなく目的にあったサイトも活用するとより満足のいく転職ができます。
おすすめ転職エージェントBEST3



ウィメンズワークスが厳選した転職エージェントをご紹介します。
転職エージェントの特徴は求人数が多いことです。
そのため、幅広いがゆえに初めての転職やどの転職エージェントを使ったらいいかわからないこともあるでしょう。
そんな方は是非参考にしてみてください。
1位.マイナビAGENT
マイナビAGENTは20代・30代の転職に強い転職エージェントです。
担当者が親身になって応募書類の準備から面接対策まで転職をサポートしてくれるので、初めて転職する方でも安心です。
第二新卒のサポートも手厚く企業担当のアドバイザーが在籍しているため、職場の雰囲気や求人票に載っていない情報を知ることができます。
転職先でうまくやっていけるか不安な方や初めての転職にはマイナビAGENTがおすすめです。
マイナビエージェントの詳細はこちら
マイナビAGENTの評判はこちら
2位.dodaエージェント



dodaエージェントは、幅広い業界や業種の求人を取り扱う国内最大級の転職エージェントです。
dodaのみが取り扱っている求人も多く、転職活動の視野を広げたい方におすすめです。
また、応募書類のアドバイスや書類だけでは伝わらない人柄や志向などを企業に伝えてくれたり、面接前後のサポートも手厚いです。
dodaエージェントは、20代30代だけでなく地方での転職の方にもおすすめできる転職エージェントです。
3位.リクルートエージェント
リクルートエージェントは多数求人を保有している、転職支援実績No.1の総合転職エージェントです。
一般公開求人だけでなく、非公開求人数も10万件以上取り揃えています。
転職において求人数が多く実績も豊富なため、必ず登録すべき1社と言えます。
また、各業界・各職種に精通したキャリアアドバイザーがフルサポートしてくれるため、初めての転職でも利用しやすいでしょう。
リクルートエージェントの詳細はこちら
リクルートエージェントの評判はこちら
おすすめ転職サイトBEST3



先述した通り、転職エージェントは求人が多いです。
しかし、エージェントに登録していない企業もあります。
転職は「情報をどれだけ集められるか」が非常に重要になります。
そのため、転職エージェントだけでなく転職サイトもぜひ活用していきましょう。
ウィメンズワークスが厳選した転職サイトをご紹介します。
1位.doda



dodaはリクナビNEXTに次いで多くの求人数を保有しており、利用者満足度の高い転職サイトです。
お気づきの方もいるかとおもいますが、dodaは転職エージェントと一体型なのです。
つまり、dodaに登録することで求人を見ることも、転職エージェントに相談することも出来ます。
情報収集をしつつ気になった企業への相談がすぐにできるので非常に魅力的な転職サイトと言えるでしょう。
転職初心者はリクナビNEXTと合わせて登録しておくことがおすすめです。
2位.マイナビ転職



マイナビ転職は、大手人材企業「マイナビ」が運営する転職サイトです。
20代〜30代前半に多く利用されている若者向け転職サイトで、若手を採用したい企業が多いので第二新卒や20代であれば転職成功に大きく近づけるでしょう。
また独占求人が多く、他サイトにない求人に巡り合うことができるのでこちらも登録することをおすすめします。
20代〜30代前半であれば登録しつつ他サイトと比較していくと選択肢が広がるきっかけになるでしょう。
マイナビエージェントの詳細はこちら
マイナビ転職の評判はこちら
3位.リクナビNEXT



リクナビNEXTは、大手人材企業「リクルート」が運営する、業界最大規模の転職サイトです。
転職をする際はまず登録すべきサイトの一つです。
リクナビNEXTの掲載求人は20代~50代までと幅広く、地域に偏らないことも大きなメリットです。
リクナビNEXTであれば希望条件に合致する求人や地方在住に関わらず、自分に合う仕事が見つかるでしょう。
また、「グッドポイント診断」を使用すれば自分では気が付かない長所や強みを見つけるきっかけになります。
これらを活用して書類作成や面接準備もスムーズに進めることができるでしょう。
リクナビNEXTの詳細はこちら
リクナビNEXTの評判はこちら
まずは派遣!そんな考えのあなたに



まずは派遣で自由に好きな仕事をしたいと思う方も多くいます。
自分にあったお仕事探しをしたい方はなるべく大手の派遣会社に登録するのが良いでしょう。
でもどの派遣会社にしたらいいかわからない…。
そんな方のためにウィメンズワークスが厳選した派遣会社をご紹介します。
1位.テンプスタッフ



テンプスタッフは日本全国に拠点が有りどの地域に住んでいても派遣の仕事が紹介されることが魅力です。
業界最大級の求人数で、幅広い業界や職種からあなたにピッタリの仕事が見つかるでしょう。
中でも事務職の求人が多く、事務職になりたい方は必ず登録しておきたい派遣会社です。
2位.アデコ



アデコは有名・優良企業の求人が多数で「今後もこの派遣会社から働きたい(再就業率)」No.1を獲得しています。
有名・優良企業の求人が多いので大手で安心して働ける環境が整っています。
わがまま条件を叶えたい方、幅広い求人から自分にあった仕事を探したい方におすすめの派遣会社です。
3位.パソナ



パソナは高時給・大手上場企業の求人が多数揃っています。
パソナは派遣会社にもかからわず月給制を取り入れており、安定的に収入を得ることができるでしょう。
更に福利厚生が充実しており、安心して派遣のお仕事に取り込んでいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。
これまでのスキルを活かして高単価で仕事を探したい方におすすめの派遣会社です。

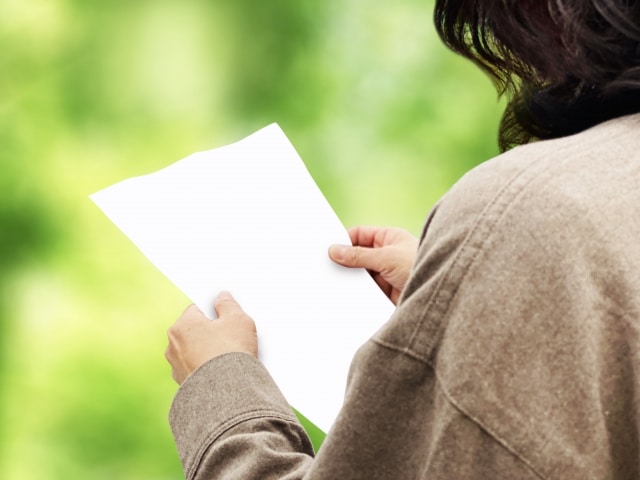
 LINEで送る
LINEで送る


