第2新卒とも呼ばれている世代に該当する新卒3年目にて、最適な転職をする方法を解説していきます。
まだ若い世代なので伸びしろがありつつも、社会人経験も身についてきた今だからこそ、どのような転職活動を展開すればよいのでしょうか?
実例も含めながら新卒3年目の転職成功のコツを紹介します。
Contents
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
新卒3年目の転職成功のコツは

新卒者が社会人として成長を遂げているかを判断する目安は入社3年目だという説が多いようです。
その理由にはいくつかの根拠があります。
3年同じ会社で勤め上げていれば、社会人としてのマナーや仕事の流れをほぼ把握したことになるのもその理由の一つです。
そこで新しい可能性を見出すために転職を考える人も増えていきます。
では新卒3年目にて、女性がうまく転職するためにはどのような方法やポイントを理解しておけばよいのでしょうか?
新卒3年目の評価されるポイント

大卒間もない新社会人が1年未満に転職をしてしまうと途端に評価が下がってしまうものです。
それに対して、新卒後3年目の社会人になればある程度の高い評価を受けます。
若い未経験な戦力をと考える企業が、矛盾を犯してまで3年も経過した人物を受け入れようとしている理由はどこにあるのでしょうか?
ここでは新卒3年目が評価されるポイントを解説します。
「やる気」を見て判断してもらえる
新卒3年目の平均年齢は約25歳から28歳くらいとみてよいでしょう。
まだその年代は仕事を吸収して身につけようとするバイタリティに溢れている世代と判断されるからです。
もちろん仕事への熱意には個人差もあります。
一般論として、20代半ばの若い世代はまだ十分な社会人経験がないことをプラスに切り替えることが可能です。
業務全般へ積極的に取り組める姿勢を高く評価してもらえるでしょう。
企業の未来の戦力としての期待が持てる年代だから重宝されます。
社会人としての基礎知識を持っている

新卒3年目と大卒初年度との違いは、すでに一定の社会人的な振る舞いができるという点です。
転職者として採用するのに大きなメリットになるでしょう。
新卒1年目の人物にはさまざまな社会人ルールを最初から指導する手間が掛ります。
それと比較しても、3年経過した人物なら、多少なりとも社会の厳しさや意義を肌で感じているはずです。
その経験値は即戦力としても機能します。企業側にとっても社員教育の時間を節約できるため好都合です。
実績をアピールできる
どの企業でも暗黙の了解になっているのが、3年も同じ仕事をすれば一通りの業務内容に精通しているという考え方です。
仕事が身について一人前な振る舞いができるのに、丁度3年あれば完成に近い姿を見ることができます。
その中で出してきた成果もいくつか存在するはずです。転職市場では応募者の過去の実績を見たいと願う企業がほとんどです。
新卒3年目の転職者ならその題材を用意できると思われています。
新卒3年目が転職活動をするタイミングは

新卒3年目の年代は転職市場で有利な立場でもあります。
ビジネスについての基礎はある程度身についていると判断でき、実務経験もそれなりに積み重ねているからです。
即戦力の期待も込められつつ、若さも備わっていることで新しい分野や経験もまだまだ吸収できます。
未経験な分野への転職には最もチャンスがある世代と思ってよいでしょう。
転職活動のタイミングとしてはベストに近いという見方ができます。
しかし選択肢が多くて内定を得やすいことがかえって裏目に出る結果になりやすい世代なのです。
何となく転職も繰り返して結局何をしたいのかも決められないまま時間ばかり経過させてしまう危険性をはらんでいます。
安易な転職をしやすいのがデメリットです。キャリアビジョンをじっくりと考えて行動することが大切でしょう。
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
新卒3年目で転職を成功させる要素

転職市場でも人気が高い新卒3年目の世代が転職を成功させるためには、どのような行動や心掛けが必要なのでしょうか?
リスクも考えられる転職活動をスムーズに展開するにはそれなりに準備が不可欠です。
ここでは新卒3年目の女性が転職を成功させるためのポイントを順番に解説していきましょう。
自己分析をしよう
年代や性別に関係なく転職のための下準備に欠かせないことは自己分析です。
そこで入社3年目を迎えた自分は転職市場でどのような価値を持っているのかを判断してみることをおすすめします。
自分の価値を見出せばその後求めたいスキルも分かってきます。
今後の自分が能力を発揮できる企業を判断できるでしょう。
自分を客観的に評価する習慣を持たないと、常に漠然とした答えしか出せなくなってしまいます。
わずか3年でも社会人経験の中で身についてきたノウハウやアピールポイントがあるはずです。
そこへ客観的評価ができるかどうかにかかわっていきます。
企業分析をしよう

企業分析は新卒3年目に限らずあらゆる世代が転職活動するために欠かせない作業です。
自分が入社したい企業がどのような商品・サービスを社会に提供して事業展開しているのでしょうか?
その企業が確実な経営戦略を練っているのかなども理解することが大切です。
少なくとも企業のホームページやSNSなどを常にチェックし、経営理念やビジョンを把握するようにしましょう。
自身のキャリアプランを明確化しよう
新卒3年目にて転職を志すのであれば、改めて将来目指そうとするキャリアプランを明確にする作業をしてみましょう。
新卒で入社した当時に行なったので必要ないと思われがちです。
しかし環境が変わることは明白なので、今度は新しい職場でのキャリアプランを立て直す必要があります。
自分が築きたいキャリアは常にアップグレードするものだと自覚しておきましょう。
新卒3年目の転職のメリット

社会人になって3年経過した時期になると、これからのキャリアを考え直して修正したいという節目に差し掛かります。
新卒としてがむしゃらに仕事をしてきた人なら、なおさらそう思いたくなるはずです。
転職市場に自分を売り込んで正当な評価をしてもらえるチャンスでもあります。
では、新卒3年目の転職を検討するメリットについて解説しましょう。
第二新卒としてチャレンジできる
まだまだ人生で働く期間が40年以上あると想定すれば、新卒3年目は新人の部類でもあります。
しかし3年でも社会人として1つの会社で仕事をやり通したことは、今後どの企業に就職しても通用する基盤ができていると見なせます。
新人でありながらも新卒以上の可能性を秘めているので、どの企業でも高い評価をしてくれるでしょう。
第二新卒として若く伸びしろがあることから転職市場でも人気があります。また、育成コストを省けることもあり企業としても利点があります。
未経験業種や業界のチャレンジもできる
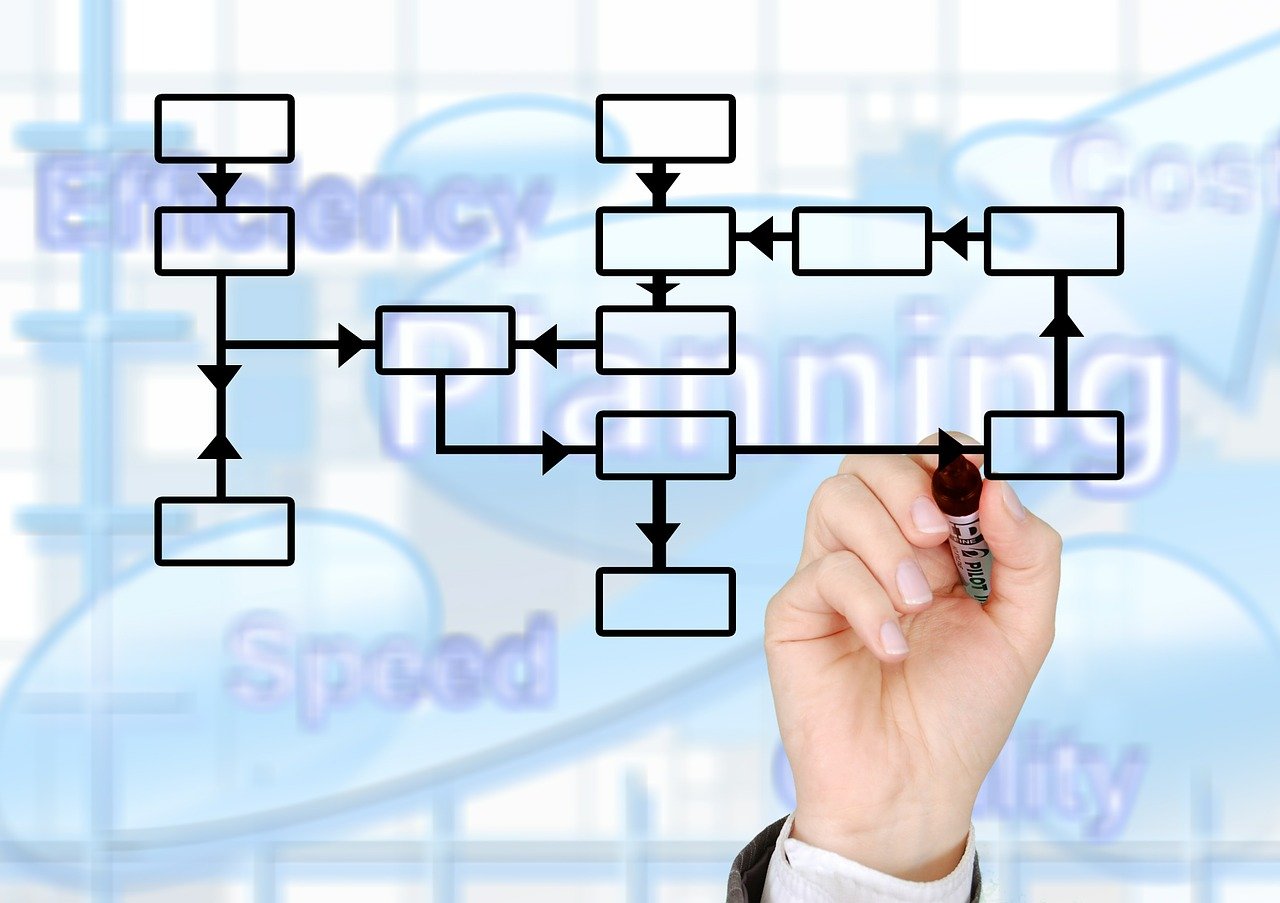
新卒3年目は第二新卒として未経験な分野へのチャレンジも可能です。
まだ入社したての1~3年目については未経験を前提に求人案件も多く出されています。
そのため異業種への転職の門徒が広いことがメリットです。
もし新卒3年目を通り越して次の時期を狙おうとすると、適合する条件は極端に減っていきます。
未経験で新しい仕事へチャレンジしたいのであれば、新卒3年までがネックになると考えたほうがよいでしょう。
パソナキャリアの詳細はこちら転職活動を始める前に気をつけたいこと

新卒3年目はまだまだニーズが高く転職にも有利な頃です。
ただしそれは一般論です。現実ともなれば、3年の社会人経験についてどう評価するのかは企業次第となっていきます。
油断は禁物と思って取りかかるほうがよいでしょう。では、新卒3年目で転職する場合に気をつけたいことを紹介します。
初めから高額な給与は期待できない
転職はそれまでの経験やスキルが重視されます。
そのためもし新卒3年目で未経験分野にチャレンジするとしたら、今までの収入相場よりも低くなることを覚悟しなくてはなりません。
もちろん一時的に収入が下がるものだと思えばよいでしょう。
その後の努力次第で収入アップは期待できます。高額な給与アップは成果を出し続けることが前提となっていきます。
専門知識が求められる企業への転職は難しい
新卒3年での経験やスキルの場合、専門知識を求めた転職案件への挑戦は険しい道のりになると思ったほうがよいでしょう。
未経験者優遇の受け入れは多くある反面、何かに特化した専門性の高い分野では、3年のキャリアはまだ経験が浅いという判断をしがちです。
多少は企業により差が生じます。
しかし専門知識や即戦力を重視する転職案件よりも、未知な期待をしてくれる企業のほうが有利であると覚えておいてください。
内定が出てから退職しよう
順番としては、まず内定を獲得してから今の会社を退職する手順を踏みましょう。
先に退職してしまうとリスクが生じやすくなるからです。退職後に転職活動を行う場合のリスクは、転職活動が長期化する恐れがあることです。
他にも、焦りや不安にさいなまれること、条件の悪い企業にしか内定が見込めないという点もあげられます。
今の会社に在籍しながら長いスパンで転職活動をしていくことで精神的に安心できるはずです。
新卒3年目の転職の実例をチェック

新卒3年目で転職を志す人にはどのような特徴があるのでしょうか?
それを客観的に判断するのであれば、実際に転職をした経験者の声を聞くのが近道です。では、新卒3年目の転職実例を見ていきましょう。
例
新卒3年目を経過してから転職をした人の中には、環境や待遇が向上したという良い例が目立ちます。
以前の職場よりも自分の時間が増えた、あるいは周囲の人間関係が良好になったという口コミが多い傾向です。
とくにパワハラに悩んでいた人が転職して成功しています。
また、女性の場合は結婚・出産といった特有な行事もあることで、上手に併行できるようになったという例も顕著です。
例
新卒3年目の転職で失敗した例の中で一番多かった声は収入の低下への不満です。
新卒から入って3年経過しやっと給与アップしたにもかかわらず、同じ相場での給与条件では良い案件が探せなかったという方が目立ちます。
今後のやりがいと現実的な金銭面のこととを考慮した上で、給与よりも新しいキャリアビジョンを描く選択をしたようです。
他には、じっくり企業研究をせずつい焦って決めてしまった会社が、入ってみるとグレーゾーンに近い待遇の悪さだったという方もいます。
転職にはある程度のリスクも覚悟する必要があるといえます。
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
新卒3年目の転職者の疑問
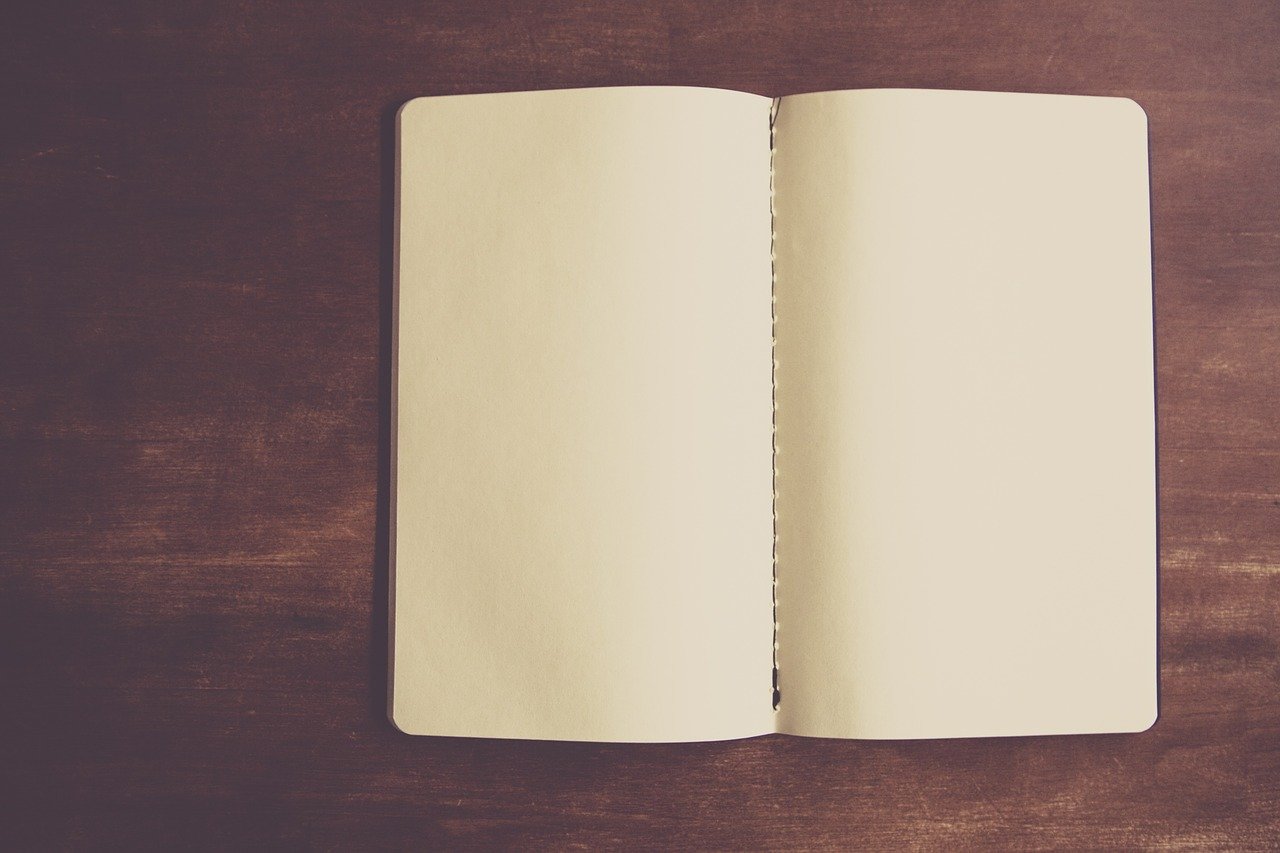
新卒3年目での転職で浮かぶ疑問点としては、実務経験が完全ではないことによるデメリットが生じる点です。
一般的に転職市場を見渡すと、実務経験が豊富だと扱われる対象は少なくとも5年以上という見方が多いからです。
3年ではまだ新米社員レベル扱いにされてしまいます。自分がチャレンジしたい業種への転職が実現しにくい場合も考えられるのです。
また、女性の場合は結婚や出産・育児などのプライベートとどう両立できるのかが問われます。
将来的なビジョンは長い目で見ることも大切ですが、直近で起こり得るさまざまな課題についても念のため考えて行動してみましょう。
転職相談は転職エージェントを活用しよう

新卒3年目では転職活動そのものが初めて経験するという方が多いはずです。
最適な求人探しができるかどうか不安を抱きやすい世代でもあります。
そこで転職エージェントの利用も考えておくとよいでしょう。
必ず専任担当者が付いてくれて、なるべく希望条件に合致する案件を紹介してくれるはずです。
それ以外にも面接対策やエントリーシートの添削といった採用試験向けのサポートも充実しています。
自分1人で転職活動に掛ける手間や無駄を簡略化できるのがメリットです。
パソナキャリアの詳細はこちらまとめ

新卒3年目での転職は次世代の可能性を期待した応募案件がほとんどです。
まだ若手の人材としての募集なので、需要も多く内定を獲得しやすい傾向があります。
しかしそれがかえって安易な決定を招く恐れを持っているのです。
焦って早く決めてしまおうとするあまり、自分の理想とかけ離れた苦労を抱えてしまいかねません。
以前の職場のほうが良かったと後悔しないためにも、新卒3年目としての転職の仕方や状況を把握しておきましょう。
成功のポイントは絶対に焦らないことです。
今の職場での仕事を続けながらでも、少しずつ転職活動の動きを広げる対策を練って臨んでみてください。
転職成功への近道は自分にあった転職サイトを見つけること!
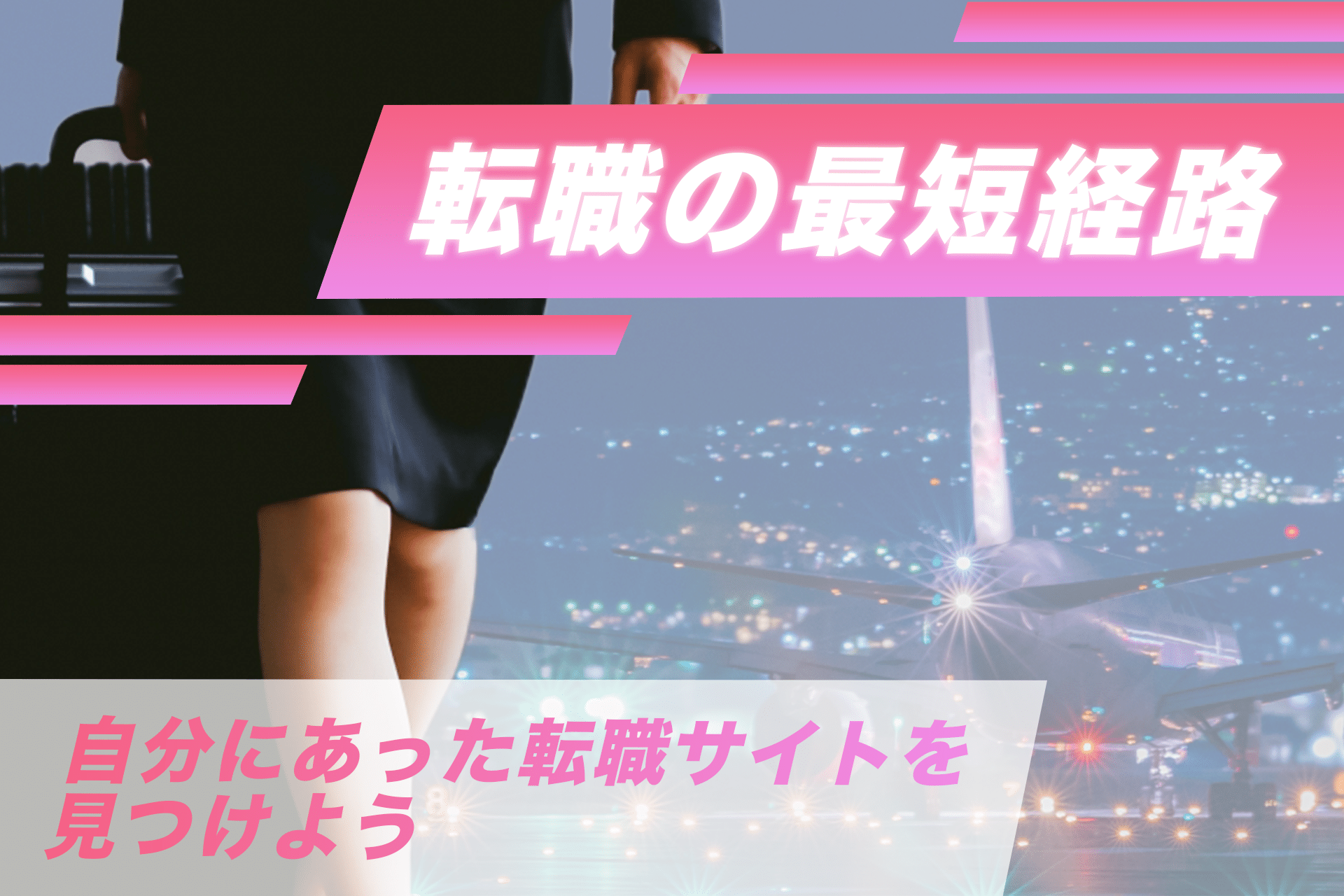
転職サイトはそれぞれ特徴や強みが異なります。
そのため、転職成功には自分の目的や希望職種にあった転職サイトを見つけなければなりません。
- 種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない
- 自分にあった転職サイトはどうやって見つければいいの?
こんな悩みをお持ちではないですか?
以下に転職サイトの選び方と比較を紹介します。
是非参考にしてみてください!
転職サイトの選び方
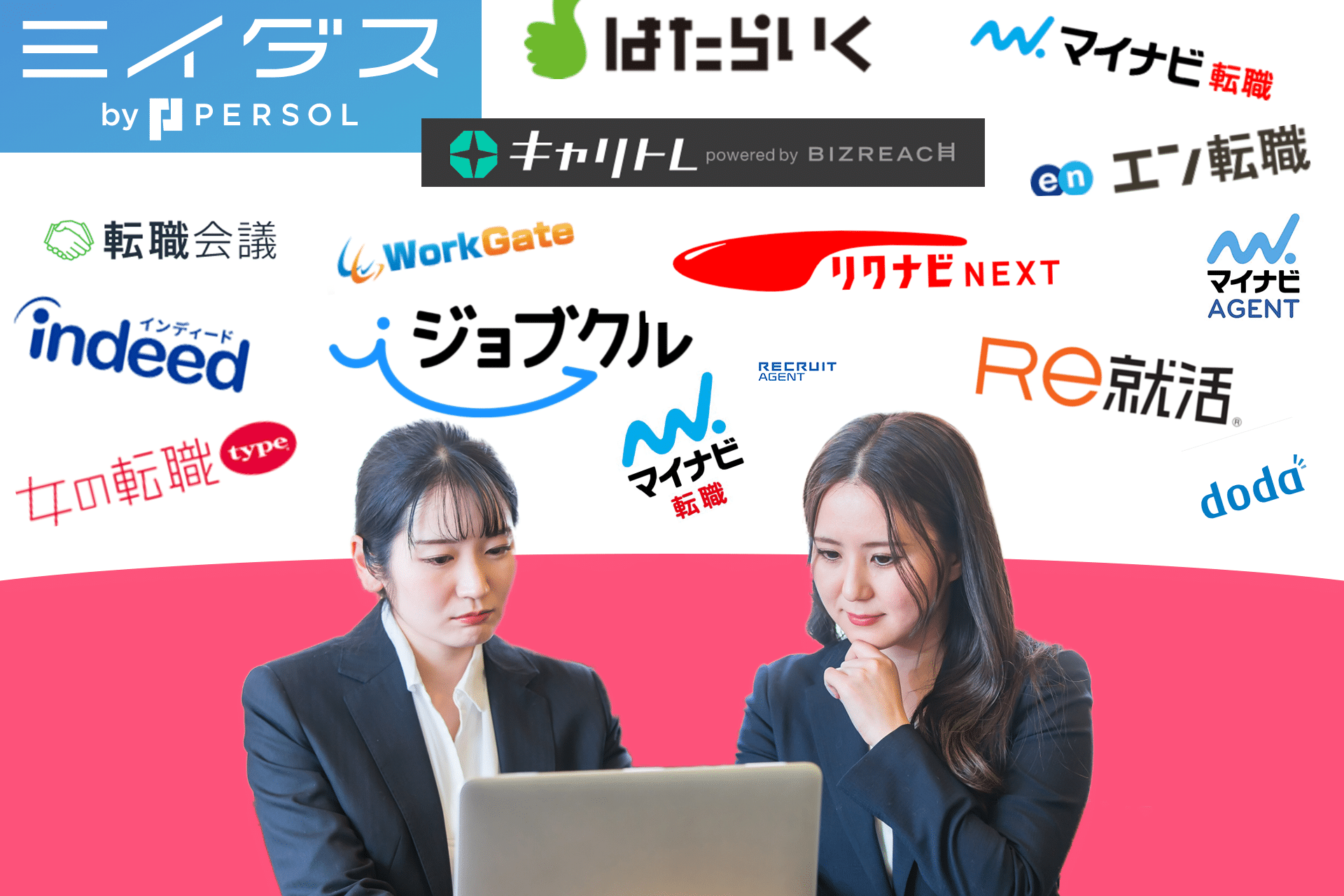
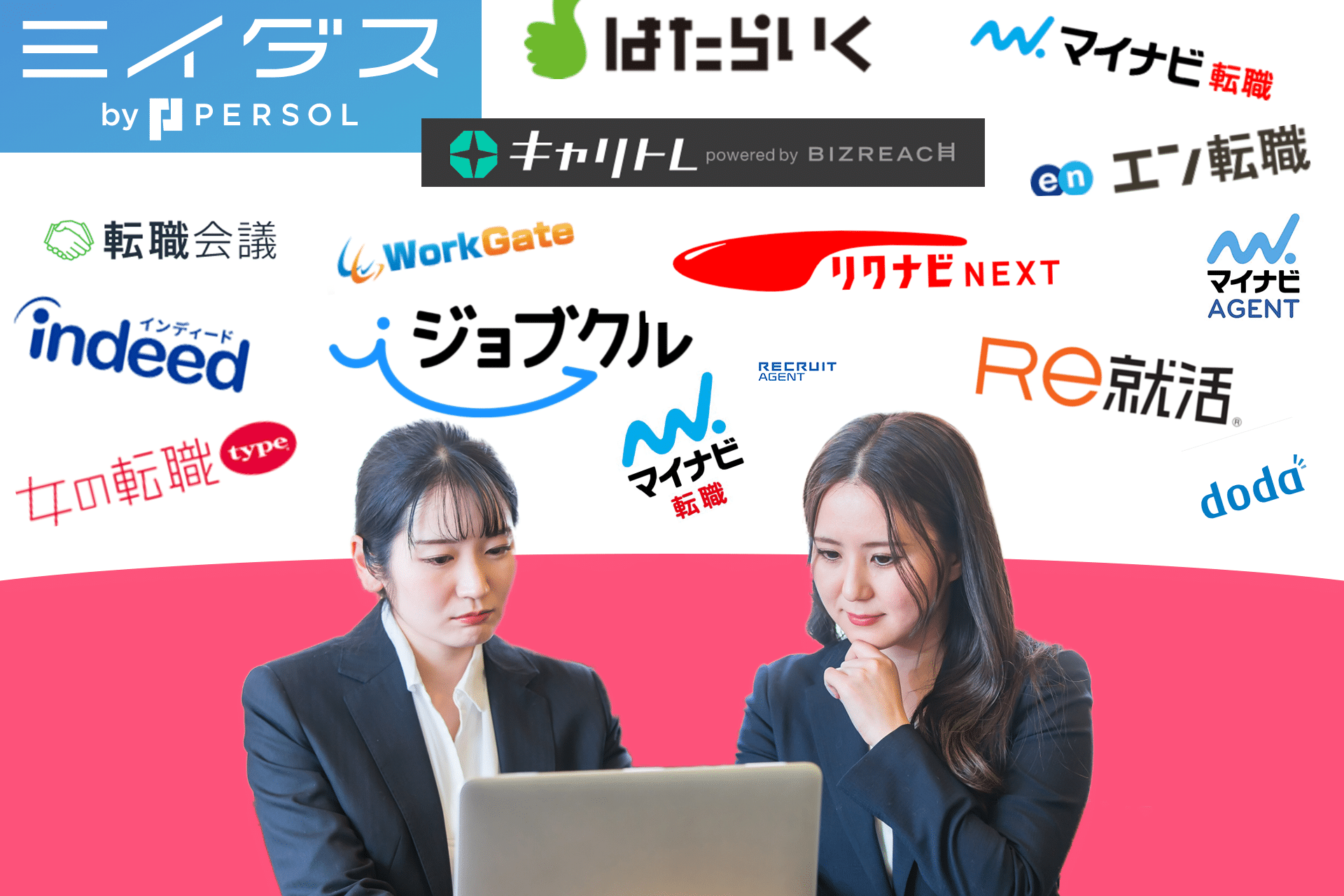
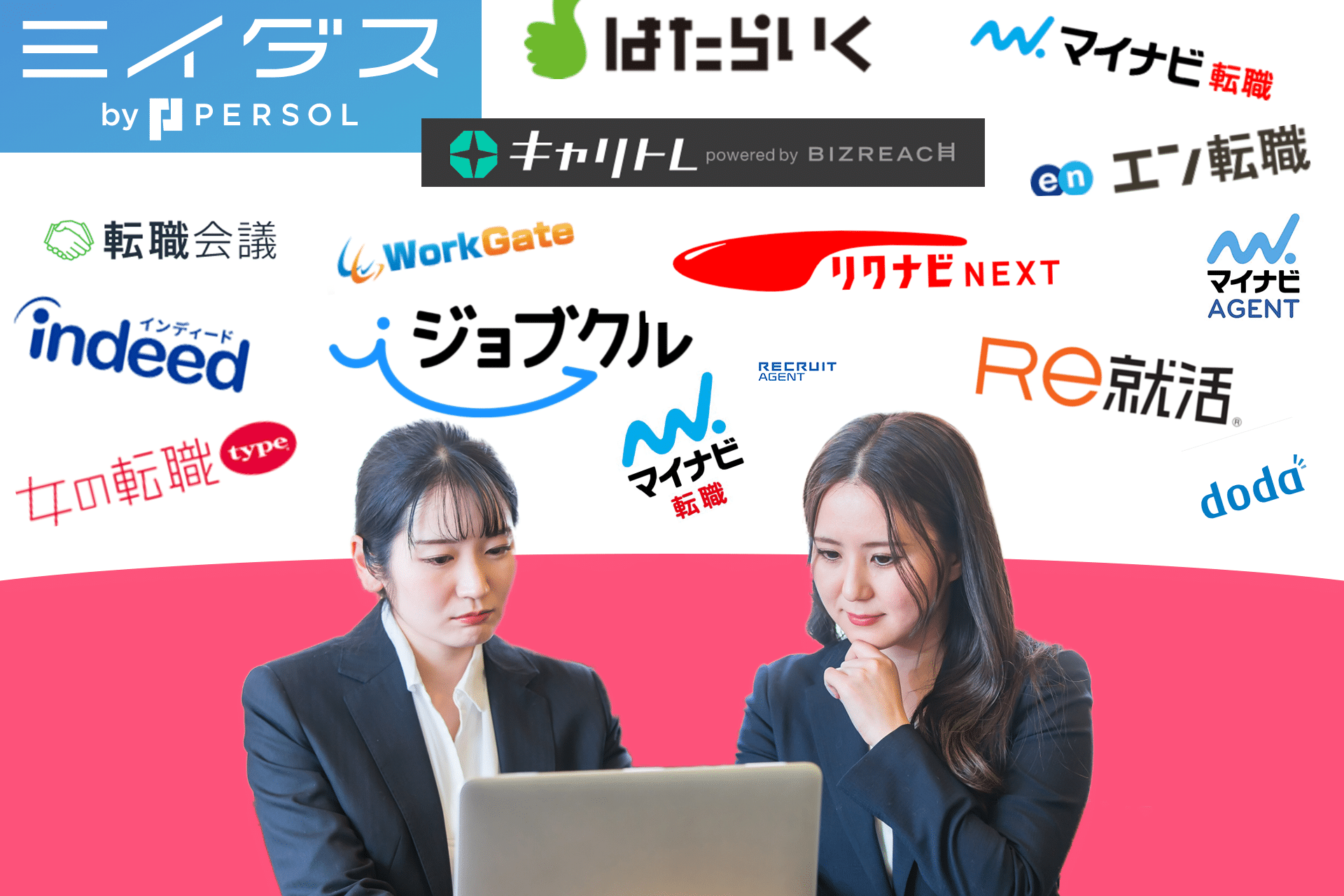
転職サイトは以下のような進め方で選ぶと最適なものを選ぶことができます。
- 「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
- 転職目的や職種など希望から選ぶ
これらをより詳しく見ていきましょう。
「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
転職サイトは大きく分けて2種類存在します。
- エージェント型:担当のキャリアアドバイザーがついて転職活動のサポートをしてくれる
- サイト(求人広告)型:求人広告が掲載されており、自身で転職活動を進める
それぞれメリット・デメリットはありますが、転職の成功率を上げるのであれば使い分けが重要です。
各サイトで扱っている求人も異なりますので少し面倒かと思っても満足のいく転職をするために使用してみてください。
転職目的や職種など希望から選ぶ
すでに転職の目的が定まっている人もいることでしょう。
そんな方は「第二新卒の活躍を支援しているサイト」や「IT業界に特化したサイト」など、幅広い支援をしてくれる大手サイトだけでなく目的にあったサイトも活用するとより満足のいく転職ができます。
おすすめ転職エージェントBEST3



ウィメンズワークスが厳選した転職エージェントをご紹介します。
転職エージェントの特徴は求人数が多いことです。
そのため、幅広いがゆえに初めての転職やどの転職エージェントを使ったらいいかわからないこともあるでしょう。
そんな方は是非参考にしてみてください。
1位.マイナビAGENT
マイナビAGENTは20代・30代の転職に強い転職エージェントです。
担当者が親身になって応募書類の準備から面接対策まで転職をサポートしてくれるので、初めて転職する方でも安心です。
第二新卒のサポートも手厚く企業担当のアドバイザーが在籍しているため、職場の雰囲気や求人票に載っていない情報を知ることができます。
転職先でうまくやっていけるか不安な方や初めての転職にはマイナビAGENTがおすすめです。
マイナビエージェントの詳細はこちら
マイナビAGENTの評判はこちら
2位.dodaエージェント



dodaエージェントは、幅広い業界や業種の求人を取り扱う国内最大級の転職エージェントです。
dodaのみが取り扱っている求人も多く、転職活動の視野を広げたい方におすすめです。
また、応募書類のアドバイスや書類だけでは伝わらない人柄や志向などを企業に伝えてくれたり、面接前後のサポートも手厚いです。
dodaエージェントは、20代30代だけでなく地方での転職の方にもおすすめできる転職エージェントです。
3位.リクルートエージェント
リクルートエージェントは多数求人を保有している、転職支援実績No.1の総合転職エージェントです。
一般公開求人だけでなく、非公開求人数も10万件以上取り揃えています。
転職において求人数が多く実績も豊富なため、必ず登録すべき1社と言えます。
また、各業界・各職種に精通したキャリアアドバイザーがフルサポートしてくれるため、初めての転職でも利用しやすいでしょう。
リクルートエージェントの詳細はこちら
リクルートエージェントの評判はこちら
おすすめ転職サイトBEST3



先述した通り、転職エージェントは求人が多いです。
しかし、エージェントに登録していない企業もあります。
転職は「情報をどれだけ集められるか」が非常に重要になります。
そのため、転職エージェントだけでなく転職サイトもぜひ活用していきましょう。
ウィメンズワークスが厳選した転職サイトをご紹介します。
1位.doda



dodaはリクナビNEXTに次いで多くの求人数を保有しており、利用者満足度の高い転職サイトです。
お気づきの方もいるかとおもいますが、dodaは転職エージェントと一体型なのです。
つまり、dodaに登録することで求人を見ることも、転職エージェントに相談することも出来ます。
情報収集をしつつ気になった企業への相談がすぐにできるので非常に魅力的な転職サイトと言えるでしょう。
転職初心者はリクナビNEXTと合わせて登録しておくことがおすすめです。
2位.マイナビ転職



マイナビ転職は、大手人材企業「マイナビ」が運営する転職サイトです。
20代〜30代前半に多く利用されている若者向け転職サイトで、若手を採用したい企業が多いので第二新卒や20代であれば転職成功に大きく近づけるでしょう。
また独占求人が多く、他サイトにない求人に巡り合うことができるのでこちらも登録することをおすすめします。
20代〜30代前半であれば登録しつつ他サイトと比較していくと選択肢が広がるきっかけになるでしょう。
マイナビエージェントの詳細はこちら
マイナビ転職の評判はこちら
3位.リクナビNEXT



リクナビNEXTは、大手人材企業「リクルート」が運営する、業界最大規模の転職サイトです。
転職をする際はまず登録すべきサイトの一つです。
リクナビNEXTの掲載求人は20代~50代までと幅広く、地域に偏らないことも大きなメリットです。
リクナビNEXTであれば希望条件に合致する求人や地方在住に関わらず、自分に合う仕事が見つかるでしょう。
また、「グッドポイント診断」を使用すれば自分では気が付かない長所や強みを見つけるきっかけになります。
これらを活用して書類作成や面接準備もスムーズに進めることができるでしょう。
リクナビNEXTの詳細はこちら
リクナビNEXTの評判はこちら
まずは派遣!そんな考えのあなたに



まずは派遣で自由に好きな仕事をしたいと思う方も多くいます。
自分にあったお仕事探しをしたい方はなるべく大手の派遣会社に登録するのが良いでしょう。
でもどの派遣会社にしたらいいかわからない…。
そんな方のためにウィメンズワークスが厳選した派遣会社をご紹介します。
1位.テンプスタッフ



テンプスタッフは日本全国に拠点が有りどの地域に住んでいても派遣の仕事が紹介されることが魅力です。
業界最大級の求人数で、幅広い業界や職種からあなたにピッタリの仕事が見つかるでしょう。
中でも事務職の求人が多く、事務職になりたい方は必ず登録しておきたい派遣会社です。
2位.アデコ



アデコは有名・優良企業の求人が多数で「今後もこの派遣会社から働きたい(再就業率)」No.1を獲得しています。
有名・優良企業の求人が多いので大手で安心して働ける環境が整っています。
わがまま条件を叶えたい方、幅広い求人から自分にあった仕事を探したい方におすすめの派遣会社です。
3位.パソナ



パソナは高時給・大手上場企業の求人が多数揃っています。
パソナは派遣会社にもかからわず月給制を取り入れており、安定的に収入を得ることができるでしょう。
更に福利厚生が充実しており、安心して派遣のお仕事に取り込んでいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。
これまでのスキルを活かして高単価で仕事を探したい方におすすめの派遣会社です。


 LINEで送る
LINEで送る


