退職するときに気になるのが、次の就職先が決まるまでのお金のこと。
退職した人は、申請した人は全員就職先が決まるまで失業保険が出る、と考えている人も多いと思いますが、実は間違いです。
実際は失業保険を受け取ることができる人とできない人がいます。さらに、受給できる期間を延長できる人とできない人がいるのです。
確実に失業保険を受け取るために、失業保険が延長できる場合の条件と手続きの方法について紹介します。
Contents
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
失業保険とは?

失業保険は公的な保険制度の1つです。正しくは雇用保険といいます。
失業した人が再就職を目指しながら、安定した生活を送れるようにするために支援する制度です。
失業保険でもらえる失業手当ては、離職した日の翌日から原則1年間と決まっています。
ただ、退職理由や被保険者だった期間によって幅があり、最短で90日。
妊娠や出産、病気などの場合は退職後90日では再就職が難しく、途中で失業手当てがでなくなり苦しい生活を余儀なくされます。
このような人たちを救うため、特別な理由がある場合は、ハローワークに申請することで失業保険の延長ができるようになりました。
失業保険をもらうにはどうすればいいか
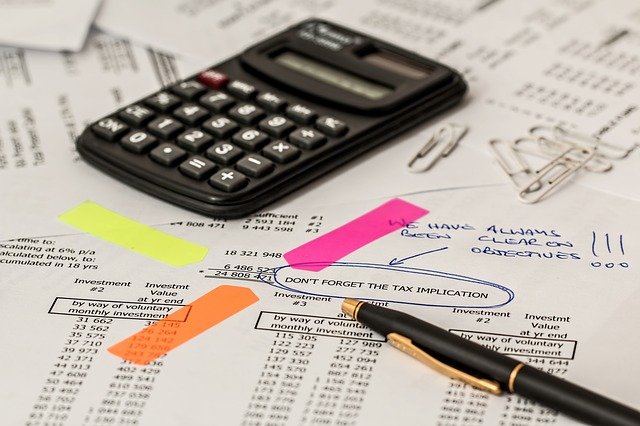
失業保険の受け取り方について知っていますか?ほとんどの人が失業保険を初めて受け取ることと思います。
初めての人でも分かりやすいように受け取れる人や、受け取り開始日についてまとめました。
どんな人が受け取れる?
失業保険を受けるための条件は2つあります。1つ目は、雇用保険に直近の2年間で1年以上加入していたかどうかです。
1年以上加入していない人は失業保険を受け取れません。2つ目は、もう一度働く意思と能力があるかどうかです。
働く意思があっても病気により働ける目処が立っていない場合は、働く能力がないと見なされ、失業保険を受け取ることができません。
基本的には、この2つの条件を満たしていれば、失業保険は受け取れます。
また、失業保険を受給するのにふさわしいか確認される機会があり、そこで認められなければ失業保険を受け取れません。
その機会は4週間に1度訪れ、過去28日分の求職活動報告を失業認定申告書に記載して申請します。
そこで認められれば、その月分の失業保険を受け取ることが可能になるのです。
その申告日を「認定日」と呼び、特別な理由がない場合は変更ができません。
いつから受け取れる?
離職した理由によって失業保険の受給日が異なります。
会社の倒産など会社都合で退職することになった場合は、受給できると分かった日の8日後から受給可能です。
逆に病気や妊娠など自己都合で退職することになった場合は、受給できると分かった日から2ヶ月と7日後になります。
自己都合の場合は日数がかかるためご注意ください。
自己都合退職でも受け取れる?
前述のように自己都合の場合でも受け取ることは可能です。会社都合で退職する場合と比べて1日あたりの支給額も変わりません。
しかし、失業保険の手当てがでる期間はどちらも1年間なので、受給開始が遅い自己都合退職ではもらえる総額が少なくなります。
健康保険や年金への影響

健康保険は日本に住んでいる人は加入しなくてはいけません。健康保険に加入する義務があるのです。
年齢も収入も関係ないため、失業中の人も健康保険に加入し保険料を支払う必要があります。
退職後の健康保険
退職後の健康保険は3つの中から選ぶことができ、それぞれ支払額が異なります。
1つ目の国民健康保険は、前年度の世帯年収と世帯人数を参考にして支払額が決定。
2つ目の任意継続制度は、在職時の健康保険料をそのまま継続します。
今までと変わらなくて良いように感じますが、在職時は会社と折半していました。
退職後は全額自己負担になるため、多額の保険料を支払う必要がでてしまいます。3つ目は、家族の扶養に入ることです。
扶養に入るため保険料を支払う必要はありません。しかし、扶養に入るための条件がいくつかあるため、それらをクリアする必要があります。
年金にも猶予制度あり
退職後であっても国民・厚生年金の保険料を支払う必要があります。
次の仕事が決まるまでの間に支払いが困難な場合は、免除制度を利用することで負担を減らすことが可能です。
前年度の年収によっては全額免除できることもあるため、上手く活用したほうがいいでしょう。
ただし、支払いをしていない期間は納付金額に換算されず、年金額が低くなります。
収入が落ち着いた後に免除されていた分の保険料を追納することができる制度もあり、減額が心配な場合は追納がおすすめです。
税金は減免になる可能性も

退職後に国民健康保険へ加入する場合、国民健康保険税が軽減されることがあります。
軽減対象者は、会社の倒産など事業主都合で退職した特定受給資格者と、雇用期間が満了などで退職した特定理由離職者です。
それらに当てはまる人であれば前年の年収を30%として保険料を計算することで、国民健康保険税が軽減されます。
ただし、同じ世帯に属しているその他の被保険者は軽減対象とならないため注意が必要です。
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
失業保険を受け取るまでの流れ

会社が発行した離職証明書を離職者が確認し、会社がハローワークに提出することで雇用保険被保険者離職票が発行されます。
雇用保険被保険者離職票を入手したらハローワークへ申請にいき、説明会に出席。
出席後、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書がもらえます。
この雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が失業保険の手当てを受け取るために必要な書類です。
その後は4週間に1度の決められた失業認定日にハローワークへ行き、失業認定を受けると失業保険手当てが指定口座に振り込まれます。
失業保険が受けられる期間は限られているため、離職票の発行は早めに発行してもらうことがおすすめです。
失業保険の延長とは?

ハローワークで必要な手続きをおこなえば失業保険の延長ができることをご存知ですか?
診断書などの延長対象だと証明できる書類が揃えば、離職日の翌日から最大4年まで延長されるのです。
ただし、申請期限は30日以上働けないと分かった翌日から1ヶ月以内です。この期限を過ぎてしまうと延長されないので注意してください。
適用される例

失業保険の延長は誰でもできるわけではありません。では、どのような人が対象なのでしょうか。
対象となる人は、早めに延長の手続きをしていたほうが後々困らなくて良いかもしれません。
妊娠・出産したとき
延長できる理由の1つが妊娠・出産です。
育休、産休は最短でも12週間とされておりますが、12週間での職場復帰は身体に大きな負担がかかります。
そのため、1年程度取得することが一般的です。
失業保険の延長制度を利用することで、子どもを保育園や幼稚園に預けたあとに再就職することができます。
子どもが4歳になる年まで手当てが給付されるため、落ち着いて育児ができるでしょう。
病気・けがの治療が必要なとき

病気やけがの治療により30日以上働けない場合も延長の対象です。
働ける状態になった後、求職活動をおこなうことで失業保険を受けとることができます。
ただし、病気やけがの治療による失業は基本手当てではなく傷病手当。
なぜかというと、雇用保険法により「働く意思と能力がある」ことを失業としているためです。
病気やけがの状態では働く能力がないと見なされ、基本手当てではなく傷病手当てが給付されます。
親族の介護をするとき
親族の介護が理由で退職した人も特定理由離職者に該当するため、失業保険の受給期間を最大で4年延長することができます。
ただし、状況によっては特定理由離職者に該当しない場合も。ハローワークの担当者や専門家に相談してください。
例えば要介護認定を受けていても、軽度で手があまりかからない場合や他に介護をしてくれる人がいる場合などは失業保険は受けられません。
延長手続きの進め方

延長手続きをおこなうには、期間が決められており書類も必要になります。失業保険を受け取り損なわないように前もって準備をしておきましょう。
手続きはいつすればいい?
いつまでに手続きをしなくてはいけない、という決まりはありません。ですが、長い人だと所定の給付日数が330日や360日の人がいます。
その場合、所定給付日数が330日の人は30日、360日の人は60日受給期間がプラス。
少し延長されるものの受給期間は変わらずに1年です。
例えば所定給付日数330日の人が退職3ヶ月後に申請をした場合、約1ヶ月分受け取ることができません。
つまり、早急に手続きをしないと受給金額の一部をもらい損ねてしまうのです。
もちろん受給されなかった日の分を、最後にまとめて受け取ることはできません。
そのため、給付日数が長く設定されている人は特に早急に手続きをしたほうが良いでしょう。
手続きはどこで行う?
住民票に記載されている地域を管轄するハローワークにておこないます。
ハローワークの必要な書類を持っていき手続きをおこなうことで受給資格が決定され、1~2週間後におこなわれる説明会に参加。
この説明会で失業保険の注意点や受給方法の説明と、認定日が決まります。その説明会に出席後、ようやく失業手当てが給付されるのです。
全国に550箇所以上のハローワークがあり、就職先を探すために複数通うことができます。
しかし、認定日に出向くハローワークも、初回の手続きをおこなうハローワークと同じところになるため、注意してください。
必要な書類は?
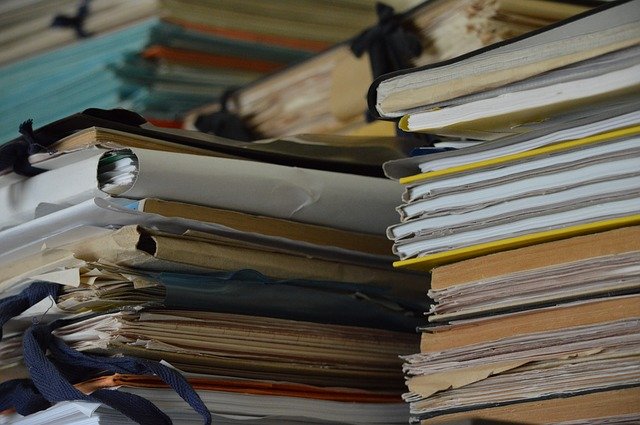
必要な書類は下記の通りです。書類が不足すると手続きを終えることができず、再度ハローワークに出向く必要がでてきます。
直前で慌てないように事前に用意をしておきましょう。
- 雇用保険被保険者離職票:以前の勤務していた会社から発送
- 個人番号が確認できるもの:マイナンバーカードや住民票
- 身分証明書:運転免許証やパスポート(マイナンバーカードがあれば不要)
- 通帳またはキャッシュカード(郵便局やインターネットバンクは振込先として登録ができません)
- 証明写真2枚(縦3×横2.5cm)
- 印鑑(シャチハタはNG)
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
手続きをするときの注意点

失業手当てを受給するときにもっとも大切なポイントは、申請期限と認定日にハローワークへ出向くことです。
特に注意が必要な期限についてまとめました。
期限内に進めよう
受給期間は1年間と決まっています。給付日数が1年を越えてしまったとしても受給期間は変更されません。
退職日の翌日から1年後から逆算をして、遅くてもいつまでに失業手当てが受給できるようにすれば良いのか把握しておきましょう。
もし期限が過ぎてしまったら?

残念ながら失業手当てを受け取ることができません。退職日の翌日から1年を過ぎた時点で、失業保険の権利が終わります。
満額受け取りたいのであれば、期間内に手続きをおこなってください。
また、申請期限が過ぎてしまう以外にも、失業保険が受け取れなくなる場合があります。
それは4週間に1度定められる認定日にハローワークに行けなかったときです。
面接や病気などやむを得ない理由の場合は認定日を変更できますが、旅行や子どものイベントなどでは変更できません。
もし行けなかったときは失業保険を全く受給できないため、忘れないようにメモをしておく必要があります。
転職活動の不安は転職エージェントに相談しよう

失業保険についてお伝えしましたが、失業保険に関わる法律は日々変わっています。
退職後どの健康保険に入ったら良いか、自分は失業保険の延長ができるのかなど不安はつきないもの。
インターネットで調べるだけでは分からないこともたくさんありますよね。
また、新しい就職先を探す際にハローワークだけでは選択肢が狭まってしまいます。
転職エージェントでは多くの企業情報を持っているので、ハローワークと併せて求職活動をおこなうことがおすすめです。
失業保険について疑問点があるときや、次の就職先に悩んだときは転職エージェントに相談してください。
まとめ
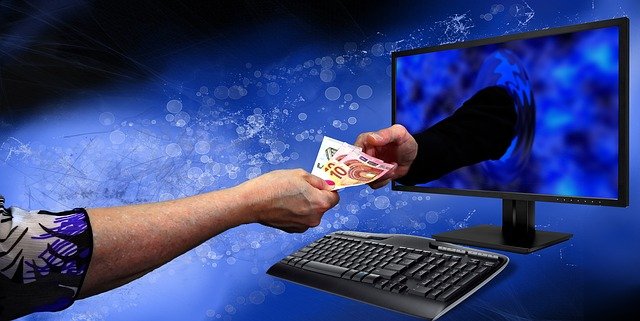
失業保険について紹介しました。自己都合の退職、会社都合の退職に関わらず失業保険は受け取れます。
さらに理由によっては期間を延長することが可能。しかし、始めにお伝えしましたが、失業保険を給付されるのは「働く意思のある人」です。
そのためハローワークで手続きをおこなう際に、求職の申し込みも忘れずにおこないましょう。
また、手続きをした後に雇用保険説明会の日程が伝えられます。
この説明会に参加しないと失業手当てが受け取れないため、忘れないようにすることが大切です。
慣れない手続きばかりでつい後回しにしてしまうかもしれませんが、失業保険が受け取れなくなる場合があるので気をつけてください。
失業保険をもらいながら、じっくり求職活動をおこない自分にあった就職先が見つかることを願っています。
転職成功への近道は自分にあった転職サイトを見つけること!
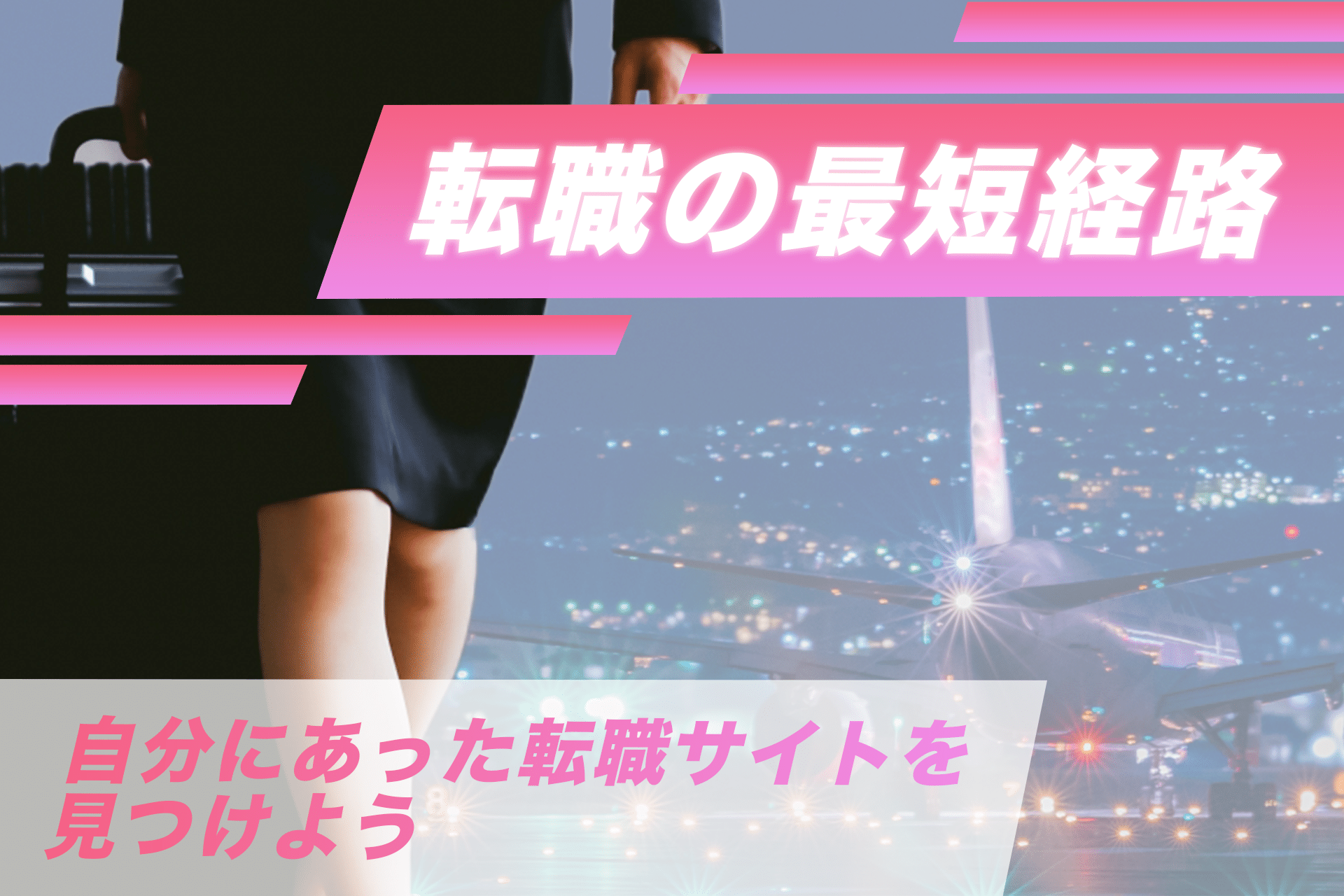
転職サイトはそれぞれ特徴や強みが異なります。
そのため、転職成功には自分の目的や希望職種にあった転職サイトを見つけなければなりません。
- 種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない
- 自分にあった転職サイトはどうやって見つければいいの?
こんな悩みをお持ちではないですか?
以下に転職サイトの選び方と比較を紹介します。
是非参考にしてみてください!
転職サイトの選び方
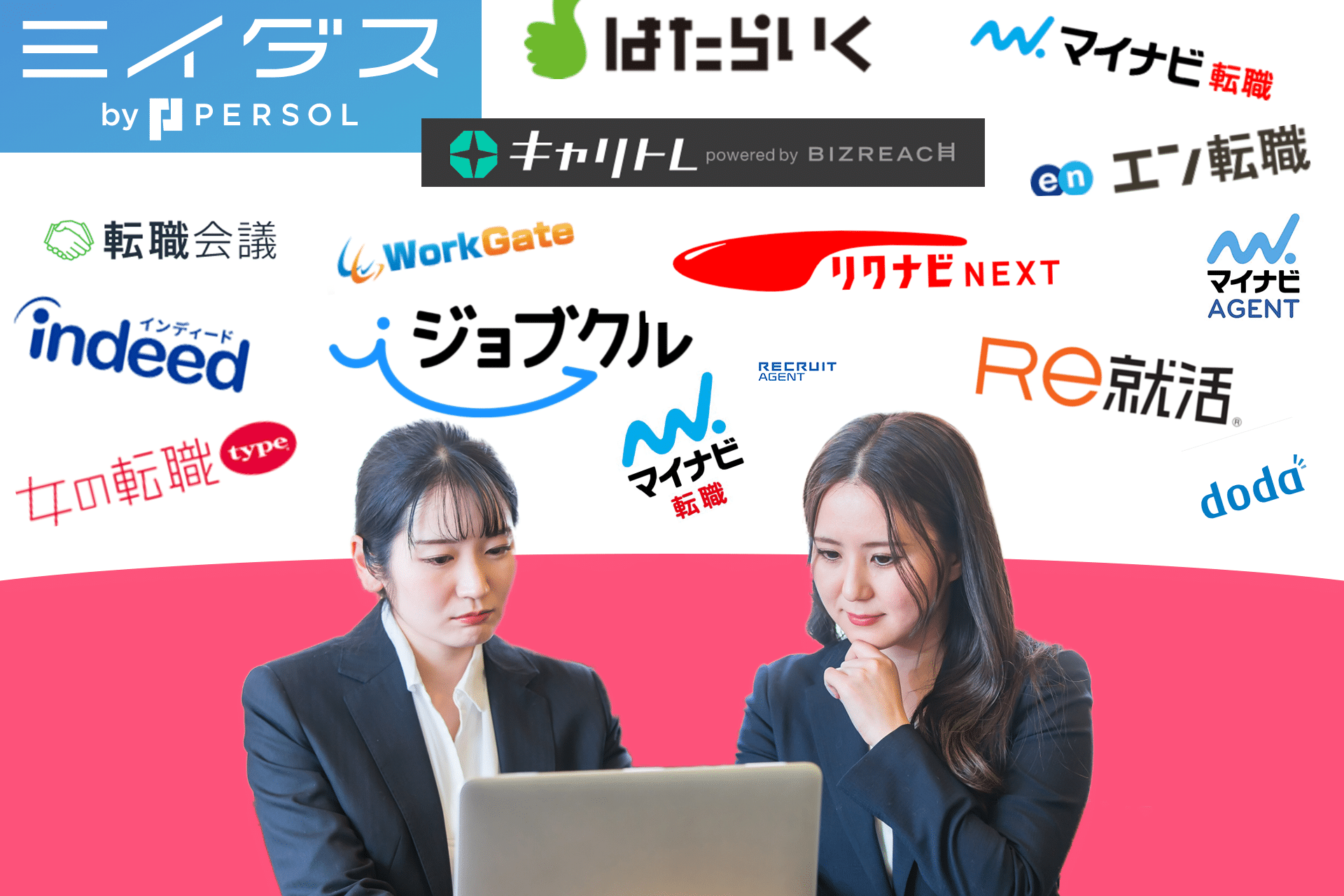
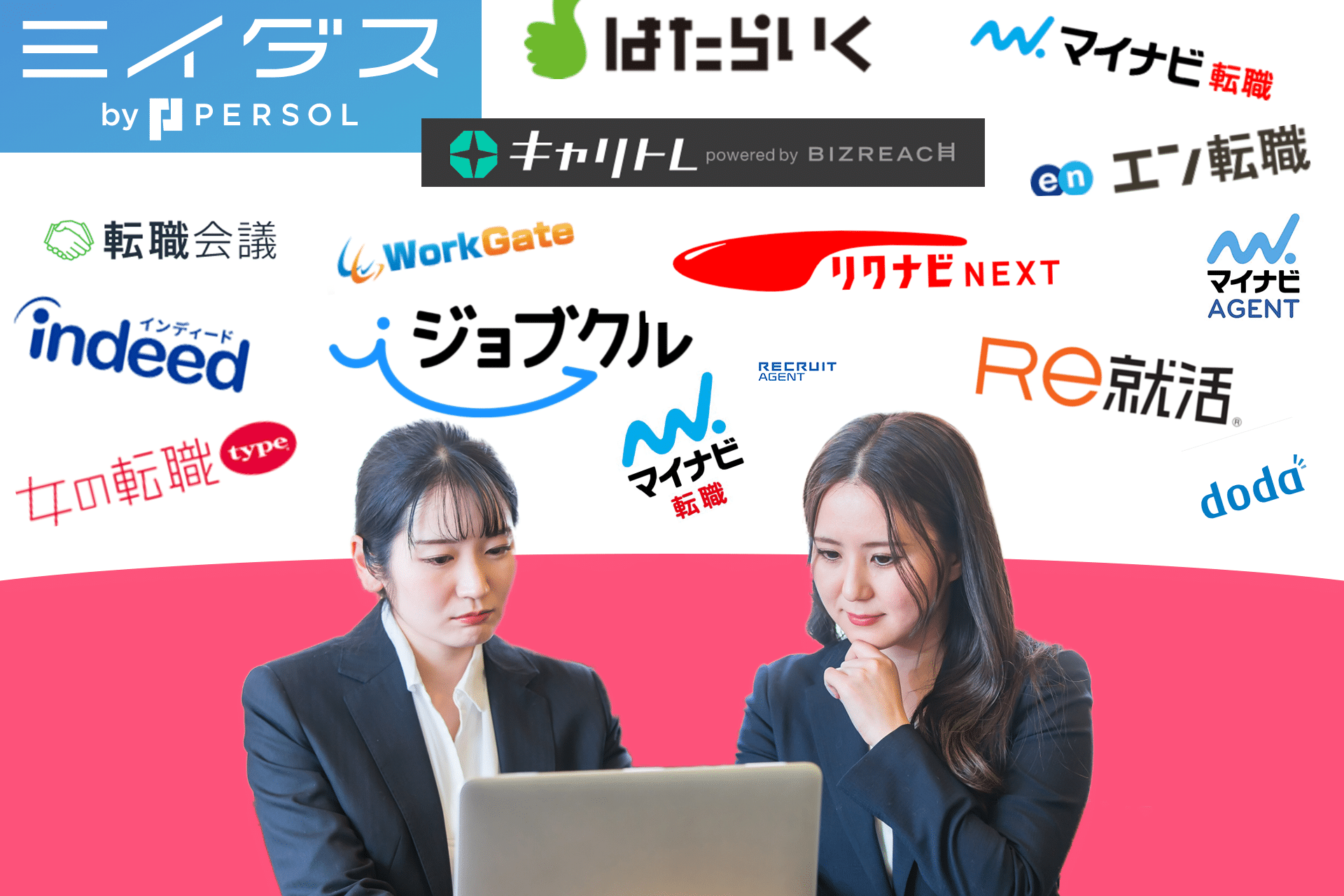
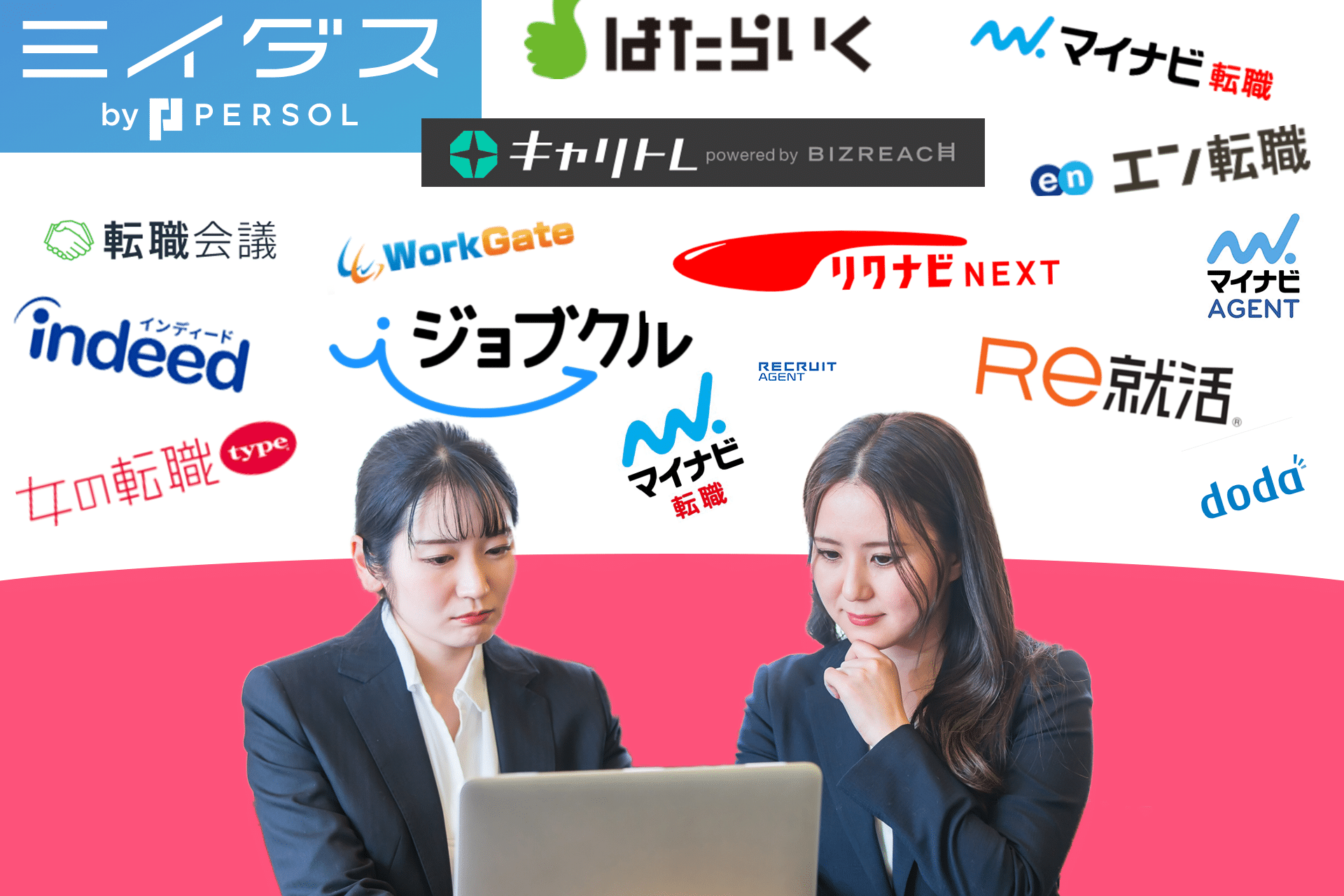
転職サイトは以下のような進め方で選ぶと最適なものを選ぶことができます。
- 「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
- 転職目的や職種など希望から選ぶ
これらをより詳しく見ていきましょう。
「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
転職サイトは大きく分けて2種類存在します。
- エージェント型:担当のキャリアアドバイザーがついて転職活動のサポートをしてくれる
- サイト(求人広告)型:求人広告が掲載されており、自身で転職活動を進める
それぞれメリット・デメリットはありますが、転職の成功率を上げるのであれば使い分けが重要です。
各サイトで扱っている求人も異なりますので少し面倒かと思っても満足のいく転職をするために使用してみてください。
転職目的や職種など希望から選ぶ
すでに転職の目的が定まっている人もいることでしょう。
そんな方は「第二新卒の活躍を支援しているサイト」や「IT業界に特化したサイト」など、幅広い支援をしてくれる大手サイトだけでなく目的にあったサイトも活用するとより満足のいく転職ができます。
おすすめ転職エージェントBEST3



ウィメンズワークスが厳選した転職エージェントをご紹介します。
転職エージェントの特徴は求人数が多いことです。
そのため、幅広いがゆえに初めての転職やどの転職エージェントを使ったらいいかわからないこともあるでしょう。
そんな方は是非参考にしてみてください。
1位.マイナビAGENT
マイナビAGENTは20代・30代の転職に強い転職エージェントです。
担当者が親身になって応募書類の準備から面接対策まで転職をサポートしてくれるので、初めて転職する方でも安心です。
第二新卒のサポートも手厚く企業担当のアドバイザーが在籍しているため、職場の雰囲気や求人票に載っていない情報を知ることができます。
転職先でうまくやっていけるか不安な方や初めての転職にはマイナビAGENTがおすすめです。
マイナビエージェントの詳細はこちら
マイナビAGENTの評判はこちら
2位.dodaエージェント



dodaエージェントは、幅広い業界や業種の求人を取り扱う国内最大級の転職エージェントです。
dodaのみが取り扱っている求人も多く、転職活動の視野を広げたい方におすすめです。
また、応募書類のアドバイスや書類だけでは伝わらない人柄や志向などを企業に伝えてくれたり、面接前後のサポートも手厚いです。
dodaエージェントは、20代30代だけでなく地方での転職の方にもおすすめできる転職エージェントです。
3位.リクルートエージェント
リクルートエージェントは多数求人を保有している、転職支援実績No.1の総合転職エージェントです。
一般公開求人だけでなく、非公開求人数も10万件以上取り揃えています。
転職において求人数が多く実績も豊富なため、必ず登録すべき1社と言えます。
また、各業界・各職種に精通したキャリアアドバイザーがフルサポートしてくれるため、初めての転職でも利用しやすいでしょう。
リクルートエージェントの詳細はこちら
リクルートエージェントの評判はこちら
おすすめ転職サイトBEST3



先述した通り、転職エージェントは求人が多いです。
しかし、エージェントに登録していない企業もあります。
転職は「情報をどれだけ集められるか」が非常に重要になります。
そのため、転職エージェントだけでなく転職サイトもぜひ活用していきましょう。
ウィメンズワークスが厳選した転職サイトをご紹介します。
1位.doda



dodaはリクナビNEXTに次いで多くの求人数を保有しており、利用者満足度の高い転職サイトです。
お気づきの方もいるかとおもいますが、dodaは転職エージェントと一体型なのです。
つまり、dodaに登録することで求人を見ることも、転職エージェントに相談することも出来ます。
情報収集をしつつ気になった企業への相談がすぐにできるので非常に魅力的な転職サイトと言えるでしょう。
転職初心者はリクナビNEXTと合わせて登録しておくことがおすすめです。
2位.マイナビ転職



マイナビ転職は、大手人材企業「マイナビ」が運営する転職サイトです。
20代〜30代前半に多く利用されている若者向け転職サイトで、若手を採用したい企業が多いので第二新卒や20代であれば転職成功に大きく近づけるでしょう。
また独占求人が多く、他サイトにない求人に巡り合うことができるのでこちらも登録することをおすすめします。
20代〜30代前半であれば登録しつつ他サイトと比較していくと選択肢が広がるきっかけになるでしょう。
マイナビエージェントの詳細はこちら
マイナビ転職の評判はこちら
3位.リクナビNEXT



リクナビNEXTは、大手人材企業「リクルート」が運営する、業界最大規模の転職サイトです。
転職をする際はまず登録すべきサイトの一つです。
リクナビNEXTの掲載求人は20代~50代までと幅広く、地域に偏らないことも大きなメリットです。
リクナビNEXTであれば希望条件に合致する求人や地方在住に関わらず、自分に合う仕事が見つかるでしょう。
また、「グッドポイント診断」を使用すれば自分では気が付かない長所や強みを見つけるきっかけになります。
これらを活用して書類作成や面接準備もスムーズに進めることができるでしょう。
リクナビNEXTの詳細はこちら
リクナビNEXTの評判はこちら
まずは派遣!そんな考えのあなたに



まずは派遣で自由に好きな仕事をしたいと思う方も多くいます。
自分にあったお仕事探しをしたい方はなるべく大手の派遣会社に登録するのが良いでしょう。
でもどの派遣会社にしたらいいかわからない…。
そんな方のためにウィメンズワークスが厳選した派遣会社をご紹介します。
1位.テンプスタッフ



テンプスタッフは日本全国に拠点が有りどの地域に住んでいても派遣の仕事が紹介されることが魅力です。
業界最大級の求人数で、幅広い業界や職種からあなたにピッタリの仕事が見つかるでしょう。
中でも事務職の求人が多く、事務職になりたい方は必ず登録しておきたい派遣会社です。
2位.アデコ



アデコは有名・優良企業の求人が多数で「今後もこの派遣会社から働きたい(再就業率)」No.1を獲得しています。
有名・優良企業の求人が多いので大手で安心して働ける環境が整っています。
わがまま条件を叶えたい方、幅広い求人から自分にあった仕事を探したい方におすすめの派遣会社です。
3位.パソナ



パソナは高時給・大手上場企業の求人が多数揃っています。
パソナは派遣会社にもかからわず月給制を取り入れており、安定的に収入を得ることができるでしょう。
更に福利厚生が充実しており、安心して派遣のお仕事に取り込んでいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。
これまでのスキルを活かして高単価で仕事を探したい方におすすめの派遣会社です。


 LINEで送る
LINEで送る


