退職すると務めていた企業から離職票が送付される決まりになっていますが、なかなか届かずに心配した経験のある女性は多いです。
離職票は様々な手続きに欠かせないものですが、すべての企業が迅速に発行してくれるわけではありません。
そこで今回は一般的に離職票が届くタイミングと、必要な時期に届かなかった場合の代替法について解説します。
Contents
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
離職票が届かないときは焦らず対応

かつての勤務先の企業風土や退職の経緯によっては、離職票の発行が遅れることがあります。
離職票が届かないことでできない手続きも多く、離職票の送付の連絡をしても埒が明かずに困ることもあるかもしれません。
ここでは、離職票がかつての勤務先が届かなかった場合の対応策について説明します。
会社側は離職票を作成しているか確認
退職して日数が経ったにも関わらず、離職票が自宅に届かない場合は、まずかつての勤務先に確認の連絡を入れましょう。
会社側はすでに離職票の発行手続きを終了しているのかを問い合わせるのです。
電話をするのが一番ですが、気が重いと感じる場合は人事部や総務部あてにメールを送りましょう。
その際、返答期日を一緒に記載しておくと、後回しにされにくいはずです。
人事担当者の手続きミスがないか確認

離職票を発行するためには、企業の人事部からハローワークに所定の書類が送付されなければいけません。
しかし、人事担当者が送付を忘れるなど、簡単な手続きミスで滞る事例があるのも事実です。
また手元に離職票があるにも関わらず、郵送を失念するケースもあります。
それを確かめるためにも退職した企業の人事部に連絡し、離職票の発行手続きがしっかり行われたかどうかを確認しましょう。
もしそこでミスが発覚した場合も、人事担当者を責めるより、迅速に対応するよう依頼するようにしましょう。
退職した会社とのもめ事は、転職に悪影響を及ぼすリスクがゼロではないので、避けた方が無難です。
ハローワークが繁忙期の可能性も
離職票は企業が作成するものではなく、ハローワークが発行するものです。
そのため、年度末や半期末など退職者が多くなる繁忙期には手続きが増え、発行が遅れる可能性があります。
その場合は企業に問い合わせた際に、ハローワークから離職票が届いていないと説明があるはずなので待ちましょう。
離職票が届かないことを会社に連絡しよう

失業保険の給付手続きなどに欠かせない離職票は、退職者にはとても大事な書類です。
しかし待っていてもいつまでも離職票が届かず、不安にかられる人も珍しくありません。
ここでは、離職票が届かないときにまず行うべき対応を紹介します。
発行依頼がなければ発行しない会社も
本来企業は退職者が出たらすぐに、離職票の発行手続きを行う必要があります。
しかし残念ながら、退職者が発行依頼をしなければ手続きを行わない、モラルの低い企業があるのも事実です。
退職を伝える段階で、離職票が必要なことは明言しておきましょう。
退職する企業に問題がありそうだと感じたら、退職日に離職票の発行手続きについて念を押しておくことをおすすめします。
手続き中ならいつ届くか確認

退職した企業が離職票を発行するための書類をいつ、ハローワークに送ったかによって、離職票の発行日が変わります。
そのため企業に問い合わせた際に手続き中といわれたら、いつ頃届く予定なのかを確認しましょう。
企業からハローワークへの書類発送が遅れたのか、ハローワークに提出済なのに返送されていないのかがわかれば目安がわかります。
ハローワークに相談しよう
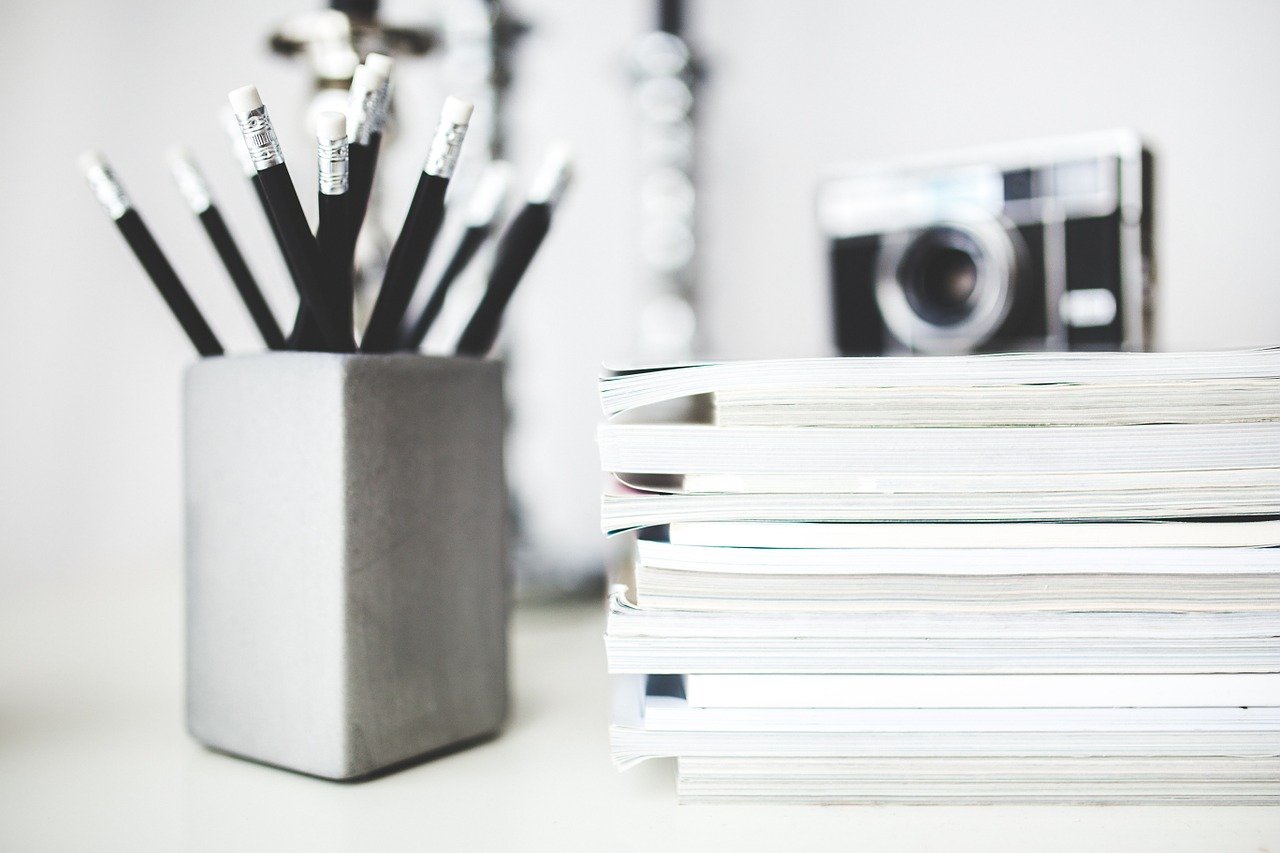
企業からは手続き中といわれたにも関わらず、一向に離職票が届かないときには、ハローワークに相談するのも方法の一つです。
ここでは、なぜハローワークに相談した方がよいのかという理由を2つ、紹介します。
ハローワークで手続きが止まっている可能性もあり
前述したように、年度末など退職者が増える繁忙期は、ハローワークで手続きが止まっている可能性を否定できません。
順次処理はしていたとしても、追いつかない量を抱えている場合は、発行を待つしか方法はないのです。
しかし、理由がハローワークにあるとわかれば、安心できるはずです。
ハローワークが会社に催促してくれることも

ハローワークに相談したことで、企業側が離職票の発行に必要な書類を送付していないことが発覚するケースもあります。
その際に自分が何度連絡しても手続きをしてくれないことを訴えることで、ハローワークから企業に催促してくれます。
これは退職日の翌日から10日以内に、離職証明書等の必要書類をハローワークに提出することが法律で決められているからです。
企業はハローワークと事を荒立てたいとは思わないものですから、迅速に手続きしてくれる可能性が高まります。
それでも効果がないときには別の手段を用いることになりますが、詳細は後述します。
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
離職票が届くまでの日数

離職票を発行するためには、企業と退職者の間で書面のやりとりがあり、それをハローワークに送る必要があります。
またハローワークからの返送手続き期間も必要なので、ある程度の日数はかかります。
ここでは、退職してから離職票が届くまでの目安の日数について説明します。
いつ届くのか
離職票を発行するためには企業と退職者、企業とハローワークのやりとりが不可欠です。
さらに書面のやりとりが郵送となるため、迅速に手続きをしても退職から離職票が届くまでに10日前後かかるのが一般的です。
企業は社員が退職して10日以内に離職票の手続きをするよう義務付けられていますので、2週間以内には届くと覚えておきましょう。
そして2週間を過ぎても離職票が届かない場合は、まずは退職した会社に問い合わせてみてください。
どうやって届くのか

離職票は退職した企業から、郵送で届くのが一般的です。
また会社がハローワークの書類を持参したとしても、ハローワークからは離職票が郵送されます。
そのため、書類提出から企業が発送するまでにタイムラグが生まれるのです。
しかし、郵送を待たずに企業に離職票を取りに行けば、受け取るまでの期間をより短くできます。
いち早く離職票を受け取りたい場合は、会社に届いたら連絡をくれるよう依頼して、自ら出向くことをおすすめします。
失業保険の手続きに間に合わないときは

いち早く失業保険の申請手続きをしたいのに、退職した企業から離職票が届かないケースは少なくありません。
失業保険の給付は手続きが遅れるとその分遅くなるため、生活に支障が起こる可能性があります。
ここでは、もし失業保険の手続きに間に合わないときにはどうすべきなのか、2つの方法を紹介します。
ハローワークで仮手続はできる
退職者本人が離職票の発行を依頼しているにも関わらず、勤務していた企業がそれを拒んでいる場合は、仮手続きすることができます。
この失業保険受給の仮手続きは、退職日から12日を経過すると行うことが可能です。
ハローワークで仮手続きを申請するにあたり、退職証明書や社会保険資格喪失証など、離職日がわかる書類が必要です。
しかし失業保険申請の仮手続きは行えても、4週間後に向かえる認定日までに離職票を用意しなければなりません。
そのため事情を説明して相談し、ハローワークから企業に催促をしてもらいましょう。
さらにハローワークから会社に指導があったにも関わらず書類提出がなかった場合は、所長権限で離職票が発行されることもあります。
またレアケースではありますが、離職後に雇用保険に加入していなかった事実が発覚することもあります。
その場合にはハローワークに、「雇用保険の被保険者の確認請求書(聴取書)」を提出するという方法もあります。
一人で悩まずにハローワークで相談しましょう。
弁護士に相談するのもあり

ブラック企業の中には、離職票の交付を拒む会社があるのも現実です。その場合、ハローワークの督促も効果があるとはいえません。
いつまでも離職票が発行されない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
法に則って離職票を発行しないような企業の多くは、サービス残業の常態化など他の労働問題を抱えている可能性が高いです。
未払いの賃金や退職金の請求の時効は2年と短いので、早々に手続きをすべきでしょう。
まずは退職した企業との交渉を依頼し、それでも発行を拒まれたら労働審判や訴訟を含めて解決の方法を提示してもらいましょう。
こんなときは離職票が届かない

企業は退職者が出たら10日以内に離職票の発行手続きを行う義務を負いますが、それが叶わないケースもみられます。
そして、どうしても離職票が届かなくなる理由があるのも事実です。
ここでは、どんなときに離職票が届かないのかについて説明します。
会社が倒産したとき
勤務していた会社が倒産したときには、離職票が届くまでに時間がかかることが多いです。
その場合はハローワークで勤務先が倒産した事情を説明することで、離職票を発行してもらえることがあります。
しかし、離職票の発行には退職日から6ヶ月以内の給与を申告する必要があり、給与明細などの証明書類の提出が求められます。
また倒産した会社に未払いの賃金や退職金があるときには、離職手続きをせずに未払い金の清算をした方がよいケースもあります。
労働基準監督署や労働問題に強い弁護士に相談し、最適な方法を見つけましょう。
会社が離職票の発行を拒んでいる

退職に際して会社ともめた場合は、離職票の発行を拒まれるリスクがゼロではありません。
退職者が困ることをわかったうえで、嫌がらせで離職票の発行を拒むのです。
会社に問い合わせても「給与計算が終わっていない」など、もっともらしい言い訳をしてズルズル引き伸ばすところもあります。
その場合は未計算と記入すればよいだけなのですが、退職者に寄り添った対応を望むのは難しいでしょう。
ハローワークに相談して催促してもらう、あるいは労働基準監督署や弁護士の力を借りるなどするのが得策です。
その際、雇用保険法第83条4項に基づいて然るべき処置をとる旨を、会社に伝えてもらいましょう。
会社が離職票を発行しないのは違法

雇用保険法では離職票の発行の元となる離職証明を退職日翌日から10日以内に発行・提出することを、雇用主に義務付けています。
つまり雇用主である企業は、退職者本人が希望した場合に、離職証明書と資格喪失届をハローワークに提出する義務を負っています。
退職者が求めたにも関わらず、会社が離職票を発行しないのは違法であり、罰則規定もあります。
理由なく離職票の請求を拒否した場合は、懲役6カ月以下もしくは30万円以下の罰金が科せられるので、提訴も視野に入れましょう。
おすすめ転職エージェント
マイナビAGENT |
doda |
リクルートエージェント |
|
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約37,000件 | 約140,000件 | 約200,000件 |
| 非公開求人数 | 非公開 | 約40,000件 | 約250,000件 |
| 対応エリア | 全国 | ||
| 特徴 | 土曜の相談も可能 | 診断・書類作成ツールが豊富 | 圧倒的な求人数 |
| こんな人におすすめ | 書類の添削から内定後のフォローまで一貫してサポートしてほしい方 | 効率的に転職活動をしたい方 | じっくり転職活動をしたい方 |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | |
おすすめ派遣会社
届いたけれど内容に納得できない場合

会社から離職票は届いたものの、その内容に納得ができないとする人が少なくないのも事実です。
具体的には会社都合での退職なのに自己都合にされている、離職日を変更されている、内容を改ざんされているなどです。
離職票を発行するためには、会社が雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書の2つを用意しなければなりません。
その手続きにあたり、給与額や退職理由について明記された書類を退職者本人に手渡し、署名・捺印をしてもらう必要があります。
しかし企業の中には、退職者本人に書類を見せることなく、別人が署名・捺印を行うなどの偽装を行うケースがあるのです。
この場合は本人と会社の交渉だけでは埒が明かないケースが多いので、労働問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
また、会社でのパワハラやセクハラが原因で退職を余儀なくされた場合、書類上は自己都合退職になることが珍しくありません。
しかし、その事実を伝えてハローワークで相談することで、調査が入り会社都合退職になったケースもあります。
泣き寝入りせずに、解決を目指しましょう。
離職票のお悩みは転職エージェントに相談

離職票の発行手続きという法律に則った手続きさえ、誠意を持って行わない企業があるのは現実です。
そんなときには、転職エージェントに登録し、離職票にまつわる問題について相談してみることをおすすめします。
転職エージェントは求人を探す場だけではなく、登録者が安心して働ける環境を紹介するところでもあるのです。
現在の悩みに真摯に対応してくれる転職エージェントは、実際に求人を探す際にも誠意を尽くしてくれます。
転職したいと考えていても、また同様の会社に勤務することに恐怖心を抱く女性もいることでしょう。
登録者の志向性と職場の雰囲気をマッチングしたうえで紹介される求人であれば、安心して応募できるはずです。
まとめ

今回は一般的に離職票が届くタイミングと、必要な時期に届かなかった場合の代替法について解説しました。
大半の企業は雇用保険法に則り、しっかりと離職票の発行手続きをしてくれるものです。
しかし中にはコンプライアンスに問題がある会社もあり、離職票が届かずに悩む女性がいるのも事実です。
その場合はハローワークや労働基準監督署、弁護士、転職エージェントなどに相談し問題を解決しましょう。
転職成功への近道は自分にあった転職サイトを見つけること!
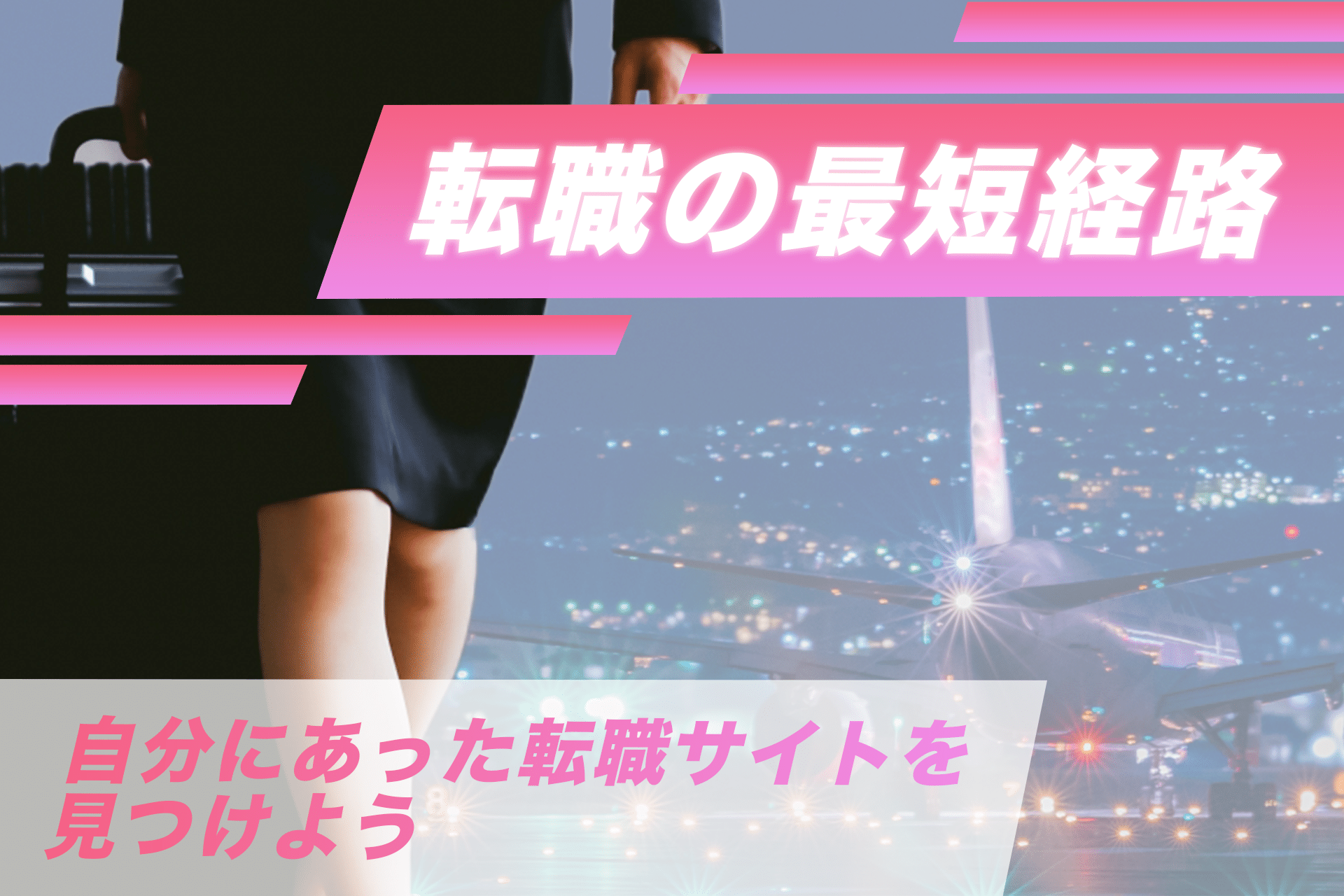
転職サイトはそれぞれ特徴や強みが異なります。
そのため、転職成功には自分の目的や希望職種にあった転職サイトを見つけなければなりません。
- 種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない
- 自分にあった転職サイトはどうやって見つければいいの?
こんな悩みをお持ちではないですか?
以下に転職サイトの選び方と比較を紹介します。
是非参考にしてみてください!
転職サイトの選び方
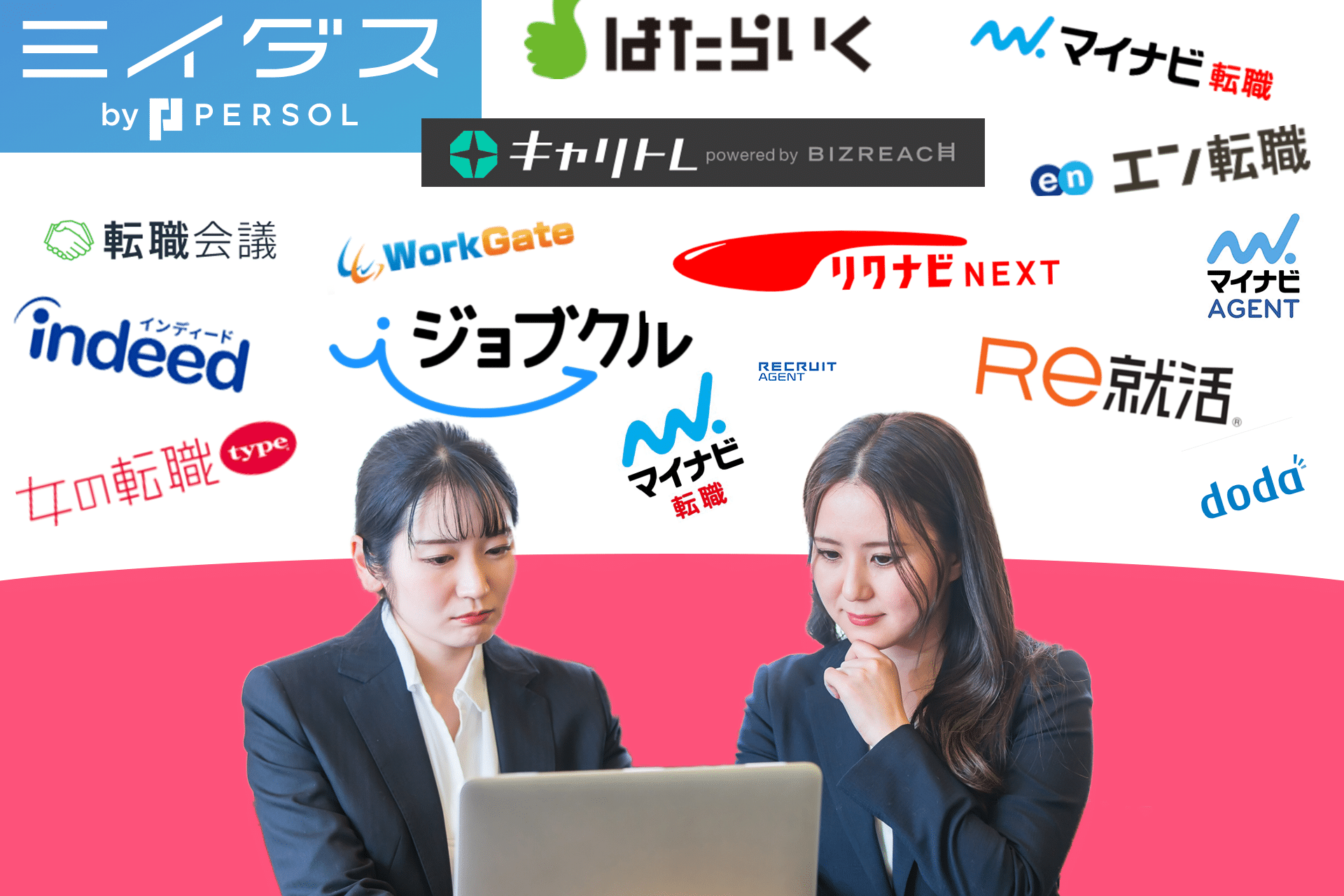
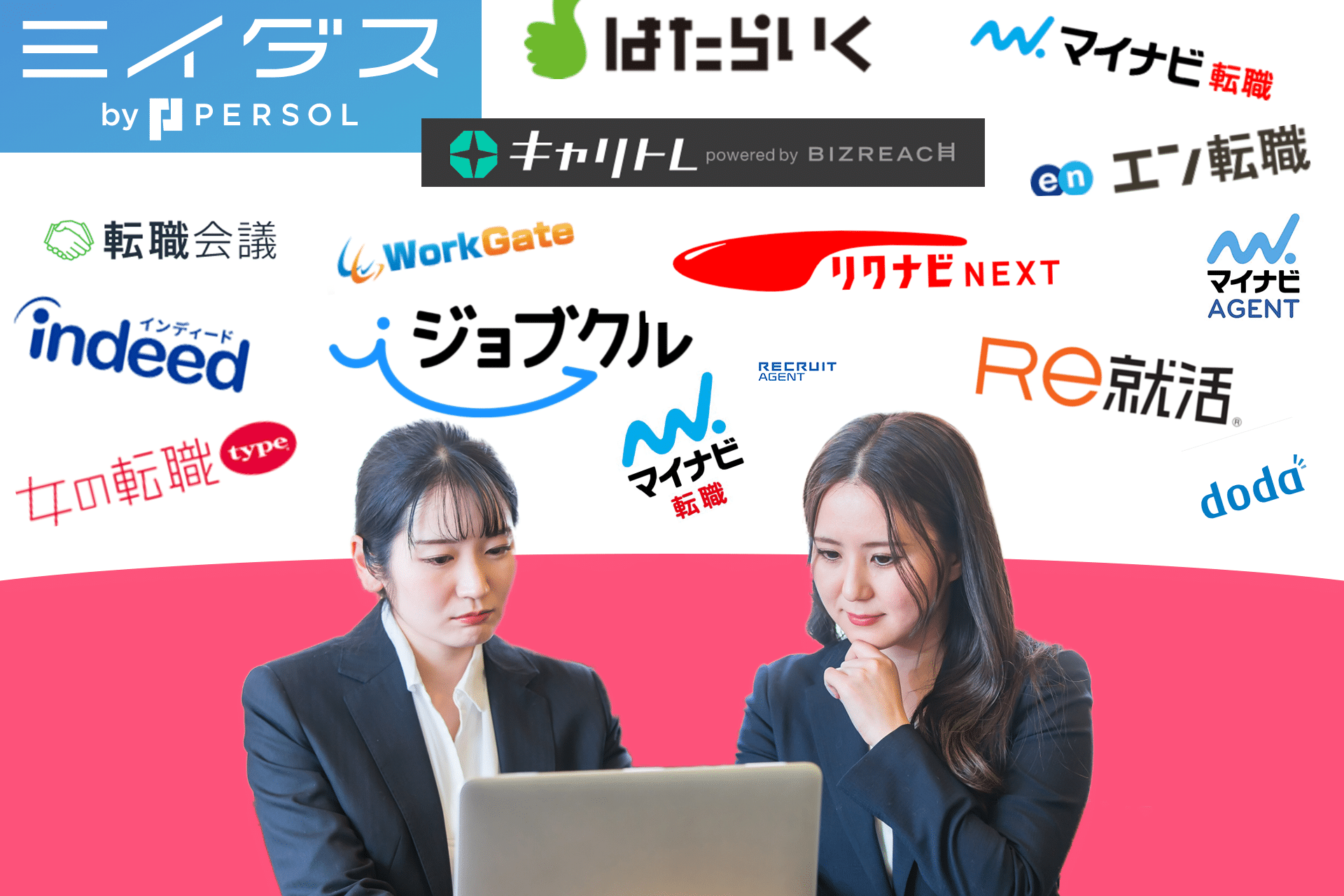
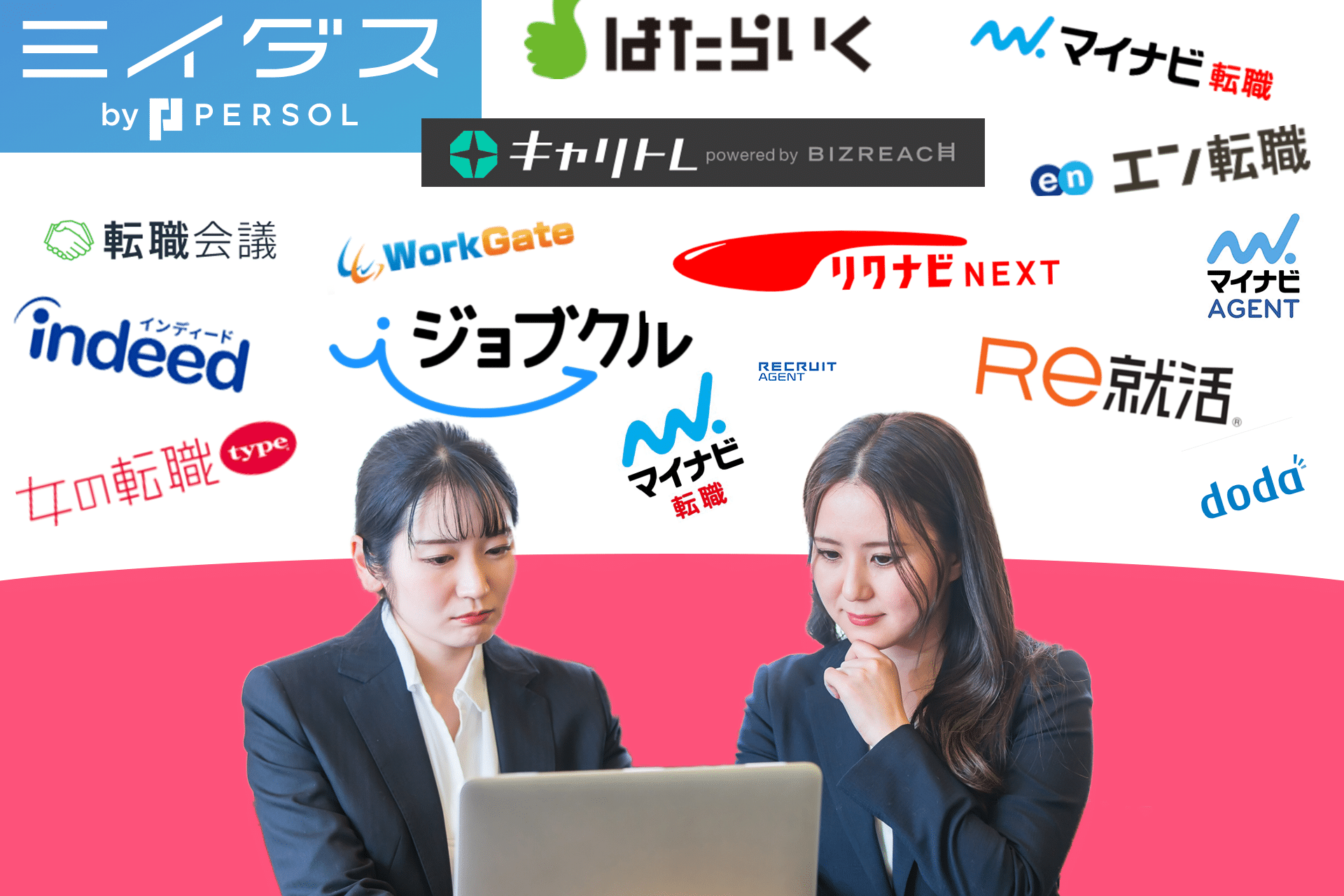
転職サイトは以下のような進め方で選ぶと最適なものを選ぶことができます。
- 「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
- 転職目的や職種など希望から選ぶ
これらをより詳しく見ていきましょう。
「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
転職サイトは大きく分けて2種類存在します。
- エージェント型:担当のキャリアアドバイザーがついて転職活動のサポートをしてくれる
- サイト(求人広告)型:求人広告が掲載されており、自身で転職活動を進める
それぞれメリット・デメリットはありますが、転職の成功率を上げるのであれば使い分けが重要です。
各サイトで扱っている求人も異なりますので少し面倒かと思っても満足のいく転職をするために使用してみてください。
転職目的や職種など希望から選ぶ
すでに転職の目的が定まっている人もいることでしょう。
そんな方は「第二新卒の活躍を支援しているサイト」や「IT業界に特化したサイト」など、幅広い支援をしてくれる大手サイトだけでなく目的にあったサイトも活用するとより満足のいく転職ができます。
おすすめ転職エージェントBEST3



ウィメンズワークスが厳選した転職エージェントをご紹介します。
転職エージェントの特徴は求人数が多いことです。
そのため、幅広いがゆえに初めての転職やどの転職エージェントを使ったらいいかわからないこともあるでしょう。
そんな方は是非参考にしてみてください。
1位.マイナビAGENT
マイナビAGENTは20代・30代の転職に強い転職エージェントです。
担当者が親身になって応募書類の準備から面接対策まで転職をサポートしてくれるので、初めて転職する方でも安心です。
第二新卒のサポートも手厚く企業担当のアドバイザーが在籍しているため、職場の雰囲気や求人票に載っていない情報を知ることができます。
転職先でうまくやっていけるか不安な方や初めての転職にはマイナビAGENTがおすすめです。
マイナビエージェントの詳細はこちら
マイナビAGENTの評判はこちら
2位.dodaエージェント



dodaエージェントは、幅広い業界や業種の求人を取り扱う国内最大級の転職エージェントです。
dodaのみが取り扱っている求人も多く、転職活動の視野を広げたい方におすすめです。
また、応募書類のアドバイスや書類だけでは伝わらない人柄や志向などを企業に伝えてくれたり、面接前後のサポートも手厚いです。
dodaエージェントは、20代30代だけでなく地方での転職の方にもおすすめできる転職エージェントです。
3位.リクルートエージェント
リクルートエージェントは多数求人を保有している、転職支援実績No.1の総合転職エージェントです。
一般公開求人だけでなく、非公開求人数も10万件以上取り揃えています。
転職において求人数が多く実績も豊富なため、必ず登録すべき1社と言えます。
また、各業界・各職種に精通したキャリアアドバイザーがフルサポートしてくれるため、初めての転職でも利用しやすいでしょう。
リクルートエージェントの詳細はこちら
リクルートエージェントの評判はこちら
おすすめ転職サイトBEST3



先述した通り、転職エージェントは求人が多いです。
しかし、エージェントに登録していない企業もあります。
転職は「情報をどれだけ集められるか」が非常に重要になります。
そのため、転職エージェントだけでなく転職サイトもぜひ活用していきましょう。
ウィメンズワークスが厳選した転職サイトをご紹介します。
1位.doda



dodaはリクナビNEXTに次いで多くの求人数を保有しており、利用者満足度の高い転職サイトです。
お気づきの方もいるかとおもいますが、dodaは転職エージェントと一体型なのです。
つまり、dodaに登録することで求人を見ることも、転職エージェントに相談することも出来ます。
情報収集をしつつ気になった企業への相談がすぐにできるので非常に魅力的な転職サイトと言えるでしょう。
転職初心者はリクナビNEXTと合わせて登録しておくことがおすすめです。
2位.マイナビ転職



マイナビ転職は、大手人材企業「マイナビ」が運営する転職サイトです。
20代〜30代前半に多く利用されている若者向け転職サイトで、若手を採用したい企業が多いので第二新卒や20代であれば転職成功に大きく近づけるでしょう。
また独占求人が多く、他サイトにない求人に巡り合うことができるのでこちらも登録することをおすすめします。
20代〜30代前半であれば登録しつつ他サイトと比較していくと選択肢が広がるきっかけになるでしょう。
マイナビエージェントの詳細はこちら
マイナビ転職の評判はこちら
3位.リクナビNEXT



リクナビNEXTは、大手人材企業「リクルート」が運営する、業界最大規模の転職サイトです。
転職をする際はまず登録すべきサイトの一つです。
リクナビNEXTの掲載求人は20代~50代までと幅広く、地域に偏らないことも大きなメリットです。
リクナビNEXTであれば希望条件に合致する求人や地方在住に関わらず、自分に合う仕事が見つかるでしょう。
また、「グッドポイント診断」を使用すれば自分では気が付かない長所や強みを見つけるきっかけになります。
これらを活用して書類作成や面接準備もスムーズに進めることができるでしょう。
リクナビNEXTの詳細はこちら
リクナビNEXTの評判はこちら
まずは派遣!そんな考えのあなたに



まずは派遣で自由に好きな仕事をしたいと思う方も多くいます。
自分にあったお仕事探しをしたい方はなるべく大手の派遣会社に登録するのが良いでしょう。
でもどの派遣会社にしたらいいかわからない…。
そんな方のためにウィメンズワークスが厳選した派遣会社をご紹介します。
1位.テンプスタッフ



テンプスタッフは日本全国に拠点が有りどの地域に住んでいても派遣の仕事が紹介されることが魅力です。
業界最大級の求人数で、幅広い業界や職種からあなたにピッタリの仕事が見つかるでしょう。
中でも事務職の求人が多く、事務職になりたい方は必ず登録しておきたい派遣会社です。
2位.アデコ



アデコは有名・優良企業の求人が多数で「今後もこの派遣会社から働きたい(再就業率)」No.1を獲得しています。
有名・優良企業の求人が多いので大手で安心して働ける環境が整っています。
わがまま条件を叶えたい方、幅広い求人から自分にあった仕事を探したい方におすすめの派遣会社です。
3位.パソナ



パソナは高時給・大手上場企業の求人が多数揃っています。
パソナは派遣会社にもかからわず月給制を取り入れており、安定的に収入を得ることができるでしょう。
更に福利厚生が充実しており、安心して派遣のお仕事に取り込んでいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。
これまでのスキルを活かして高単価で仕事を探したい方におすすめの派遣会社です。


 LINEで送る
LINEで送る


